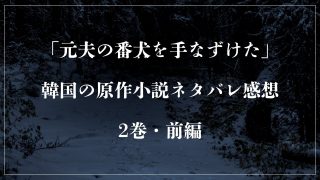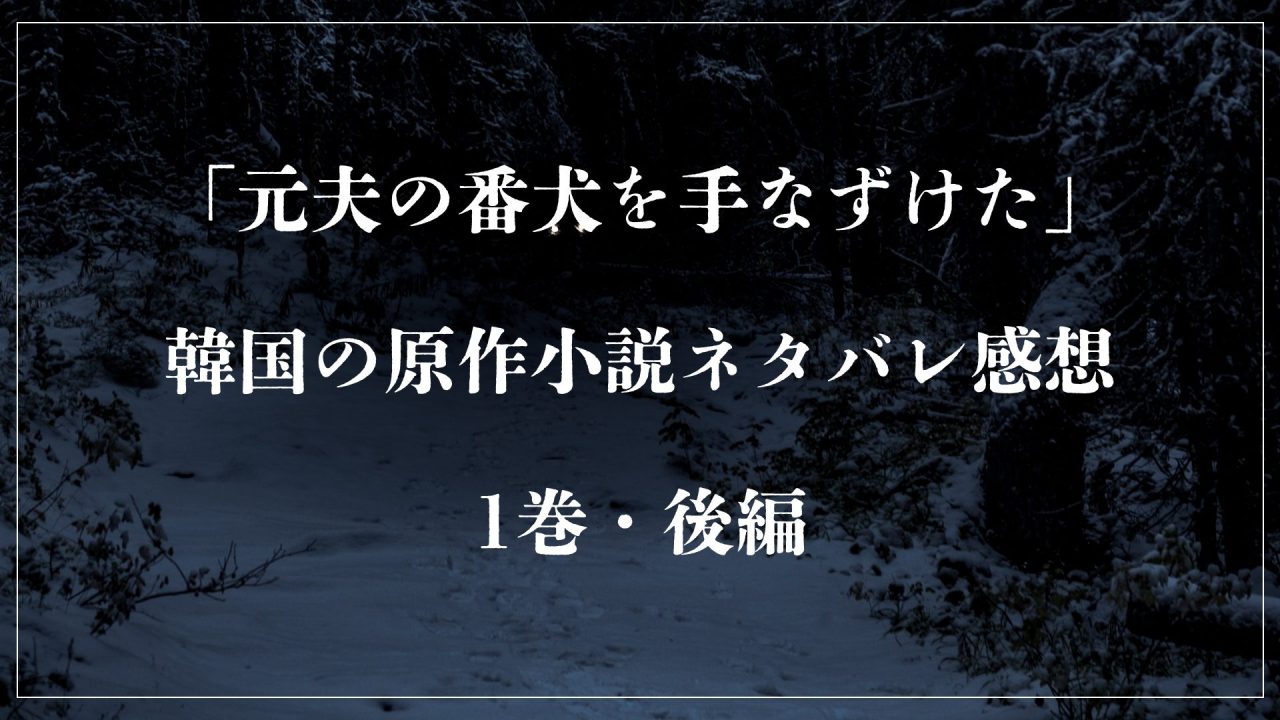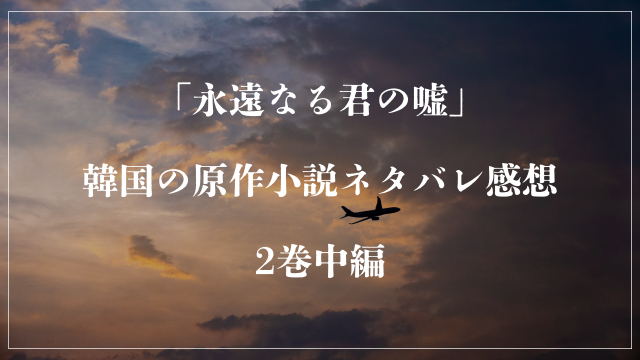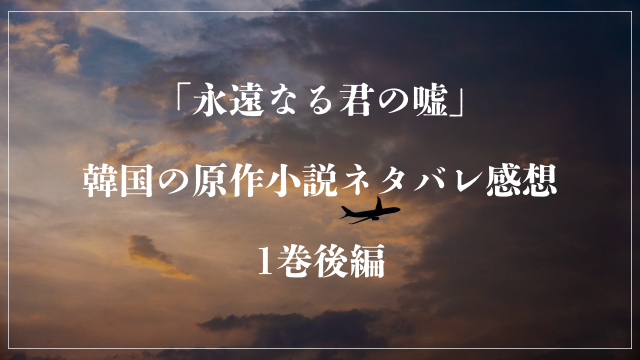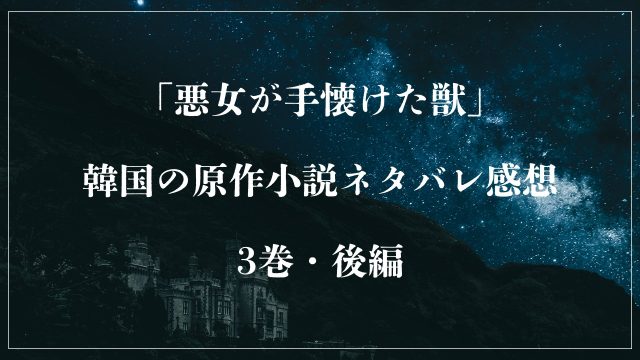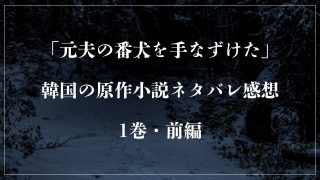コミカライズ連載している「元夫の番犬を手なずけた」の韓国原作小説を読んだのでネタバレ感想を書いていきます。韓国語は不慣れなので翻訳が間違っていることもあります。
(間違っているところを見つけた場合はtwitterのDMでコッソリ教えてください…)
元夫の番犬を手なずけた(전남편의 미친개를 길들였다)
原作:Jkyum

4.三度目の夏のバラ
サラ婦人からディートリッヒやビルヘルム達が約3年ぶりに北部から帰ってくると聞いて、ラインハルトは喜びました。
ナダンティンはルーデンから騎士を一人借りるかわりに、快くレイラン湿地をルーデンに渡し、そしてその二ヶ月後に大きな後悔をしました。ラインハルトが泥炭を掘り当てたからです。北東部では炭は金に等しい。ナダンティンは慌てて過度な支払いだったので半分返せと言ってきましたが、ラインハルトは「皇室の一族が書いた本を読まないのが悪い」と返答しました。リル・アランカスの書いた本には、泥炭のことが書かれていたのでそれを理由に使いました。
ラインハルトは泥炭を売ることに成功し、領地民にも支給したため、冬は暖かく過ごすことが出来ました。噂を聞き付けて人が移住し、不足していた警備兵も賄うことができました。おまけに、前回の人生でラインハルトが浴びるように飲んでいた泥炭から作る酒をルーデンから売り、ルーデンの領地は前より少し裕福になりました。サラ婦人と壊れた蝶番の修復や、ラインハルトの新しいドレスについて話をするほど、余裕があるようになりました。
前回、ラインハルトが反乱のために3千の兵士を集めていても首都まで話が回らなかったのは、ラインハルトの人徳によるものだった。豊かな金と心。それを渡すと、人々の見返りもまた良いものだったので、今回も同じようにして、ラインハルトは距離があった領民からの心を得ることに成功しました。
本来なら春には毎年集結する戦争はビルヘルムが野蛮族の大族長の息子を殺したことで長引き、それによってナダンティンもレイラン湿地のことに構っていられなくなりました。むしろ、大族長の息子を殺した功績によってナダンティンは多くの配当金を貰えました。
しかし、大族長は息子が殺されたためさらに戦争は大きくなりました。本来なら収穫のために自分たちの土地に帰る野蛮族は、収穫を諦めて領土侵略を進めました。
侵略を受けていたグレンシアの領主は、ビルヘルムが大族長の息子を殺し、そして大族長までも追い詰めたと知り、感嘆して、金を払うから自分の元へ来る様に誘いました。それをディートリッヒが止めた、という手紙を読んで、ラインハルトは笑います。
「戦場で盲目的になる傾向があることを除けば、とても良い騎士に成長しました。しかし他の兵士と仲良く出来ないので、兵士としては最悪です。俺の最初の弟子がこれだなんてエルンスト家の不名誉です」
それは春先にディートリッヒから送られた手紙でした。7人いる族長のうちすでに6人が死に、大族長を追撃するところなのでもう少ししたら戦争が終わります。
「兄さんから手紙をもらいました。 兄嫁が子供を産んだそうです。 このうんざりする徴集が終わったら休暇をください。 甥の顔は見るべきではないですか」
その手紙が入った包みの中には布切れの上に短く曲がった別のメッセージも一緒にあった。
「毎日剣を見ながらあなたのことを考えます」
誰の字かは明らかだった。 ラインハルトはその布切れを見て少し泣いた。 懐かしいからだ。
そして城門の蝶番、自作の新しいオーダーメイドドレスを論じたその夕方に悲報が舞い込んだ。 戦争が終わって無事に帰還すると思っていた人の死亡ニュースだった。 ディートリッヒ・エルンストの。
その訃報は、サラ婦人の娘であり、兵士として出征していたマルクが急報としてルーデンにもたらしました。ディートリッヒは最後の戦争で、その命を散らしました。
グレンシアの城壁と前哨基地の二箇所を攻められ、前哨基地にいるディートリッヒの方に支援軍が行くのが遅れてしまった。ビルヘルムが向かっていたが、途中に大族長が現れ、二人の戦いは長引き、ビルヘルムがようやく大族長の首を切る時には既に夜明けを迎えていました。グレンシアが、帝国が長らく相手にしていた野蛮族との戦いに終止符が打たれたが、ディートリッヒの命も終わってしまった。
ラインハルトは床を拳で叩き、顔を覆って動物のように泣きました。ラインハルトがディートリッヒの手紙を読んで笑っていた時、彼は既に死んでいた。
ラインハルトはついに悲鳴を上げてしまった。 ディートリッヒ。 私の幼なじみ。
幼い頃、同じベッドに横になって並んでリンケ侯爵が聞かせる昔話を聞いていた彼女の友人は、その首を野蛮族の手の下に垂らした。
ラインハルトはビルヘルムがどうしているかをマルクに聞くと、マルクは急報を知らせるために出発したため、3日間ディートリッヒの棺をビルヘルムが守っていたはずだと答えました。
そうして一ヶ月後、11人の兵士とビルヘルムがルーデンに戻ってきた。領民が飛び出して兵士たちを迎え入れ、その家族が泣いて喜んだが、その兵士の中に一人、背が高く、黒い皮の外套をつけた男、ビルヘルムがいました。
城の中庭の奥に立つラインハルトの黄金の瞳に涙が溢れて、自分の方へ足を進めたのを見て、ビルヘルムは喜びました。しかし、ラインハルトはまるでビルヘルムが見えていないかのように通り過ぎ、かわりにディートリッヒの、何も入っていない棺桶に足を向けました。ラインハルトは泣くのを堪え、出征した兵士たちに報奨金と贈り物を渡しました。
エルンストからは長男がやってきました。バーデン・エルンストは弟の遺体も何も無い棺桶を見て涙ひとつ見せず、去り際に「私の弟はあなたを選択し、これはその結果です。私はディートリッヒの選択を尊重します」と言いました。
葬儀を終えたラインハルトは自室で力なく寝転がりました。せっかく帰ってきたビルヘルムに構うことができなくて気になっていたけれど、疲れていて動けなかった。少しだけ寝ようと思ったけれど、背中のレースアップにされている紐が自分では解けず苦戦していると、扉が開く音が聞こえました。幼い女中のトロエかと思い、「悪いけど背中の紐を解いてくれない?」と声をかけます。
なんだかいつもと足音が重そうに聞こえる。そう思いながらも自分の髪を解こうと手を挙げた時、背中に暖かい手のひらが触れ、「俺に言ったんですよね?」と耳元で低い声が響きました。
「……ビルヘルム」
元々暗い印象の子供だったが、それは家族から愛情を貰えず飢えていた子供特有のものだとラインハルトは思っていました。しかし、目の前にはもう子供とは呼べない男がいて、ラインハルトは脅威を感じました。しかし、疲れからラインハルトが額を押さえるとすぐに離れ、ラインハルトがビルヘルムから感じていた脅威が立ち消えたのでラインハルトは自分が見たのは幻影だったのだと思いました。ラインハルトはビルヘルムに謝ります。
「あなたも悲しいだろうに、私はあなたの面倒も見ないで…」
ラインハルトは戸惑うビルヘルムに構わず彼を抱きしめました。ビルヘルムの髪が伸びていて、ラインハルトは自分が切ってあげたことを思い出して、泣きました。またラインハルトが謝ると、ビルヘルムはおずおずと手を伸ばしてラインハルトを抱きしめます。
「よく帰ってきたね。ビルヘルム、戻ってよかった」
「会いたかったです、ライン」
「私も会いたかった」
泣き続けるラインハルトをしっかりと抱きしめたビルヘルムは、ラインハルトの耳元で「あなたにどれだけ会いたかったことか」「暗い夜ごとにあなたを思い出していた」と繰り返し、ラインハルトが眠りにつくまでそうして囁きました。
ディートリッヒの墓石は、ラインハルトの執務室からよく見える丘に作られました。ラインハルトの元にはそれ以来、泣く暇もなく仕事が舞い込んできていました。グレンシア領地の息子であるペルナハは葬式後も滞在し、それが食糧を圧迫していたので、ペルナハを呼び出し、「あなたの馬がうちのロバの餌を食い荒らしている」とラインハルトは文句を言いました。
ペルナハの滞在の理由は明確で、ビルヘルムのためだった。10万アランカを提示されたが、ラインハルトは受け入れるつもりはありませんでした。ペルナハはラインハルトの横に立っていたビルヘルムに毎年5000アランカを支給するし、自分の娘も嫁に出すことも仄めかしたが、ビルヘルムは「興味ありません」と返答します。
要求が通らなかったペルナハがとぼとぼ部屋を出ていき、ラインハルトは「上司としてあんな人に仕えるのは大変だったでしょう」とビルヘルムに尋ねると、ビルヘルムは「あんな方ですから戦場では人気がありました」と答えました。
「あなたは?」
「……俺ですか?」
「そう。こんなにハンサムなんだから女性兵士達に人気があったと思うけど」
否定するビルヘルムに「うそ」と返しながら、ラインハルトはビルヘルムを座らせ、鏡を持ってきた。
「前髪が目に入るね。ちょっと整えてあげる」
「大丈夫……」
「以前のようにはならないから任せて」
3年間、ラインハルトは女中たちの髪の毛を切ってあげていたので腕前が上がっていました。前髪を避けると、驚くほど美しい顔の男がいました。色事にあまり関心のないラインハルトでさえドキドキするような魅力的な顔だった。ラインハルトが以前のように頭を撫で回すと、ビルヘルムは少し困惑したあとに笑いました。
「ライン、あなたが言ったことだけを考えて戦いました。必ず生きて帰ってこいって」
ビルヘルムはラインハルトの手を掴んでそこに自分の頬をこすった。それが犬のように可愛くて、ラインハルトが思わず頬を撫でると、ビルヘルムは一瞬固まりました。
「あの、ライン。欲しいものがあります」
「何が欲しいの?」
「まだ言えません。今度、話します」
鏡越しに映るビルヘルムの瞳はまっすぐラインハルトを見ていて、何となくラインハルトは鳥肌がたち、ビルヘルムの頬をつねった。
「立派に戦争で活躍した騎士に領主が褒美を与えるのは当然だけど、あまり遅いなら無しになるわよ」
「手遅れになる前に言います」
ビルヘルムは19歳になりました。戦場を経てすっかりと成長した姿になりましたね。
ペルナハは与えられた客室で不満を言っていたけれど、同時にラインハルトについて交渉術に長けた女であることを評価していました。馬の餌代を引き合いにされれば、ペルナハは羞恥心から帰るしかない。馬の餌代をわざわざ計算して差し出すわけにもいかないし、差し出したら差し出したらでラインハルトは当たり前のようにそれを受け取るでしょう。
ペルナハは「グレンシアのキツネ」と呼ばれるほど、交渉術に長けている男だった。これまで色々な婦人に会ってきたが、まだ30歳も越えていないのに、ラインハルトは老練した婦人のような印象を受けました。
「よし、妹の肖像画を持って再挑戦しよう!」
ペルナハの妹は本当に綺麗だったが、しかし隣でそれを聞いていた副官のアルゼンは「坊ちゃんの命が危険なので辞めた方が良いかと…」と忠告しました。
その時、大きめのノックがされた。訪ねてきたのはビルヘルムだった。
ペルナハはラインハルトの前でできなかった交渉をするために来たのだと喜んだが、アルゼンはそうではなかった。ビルヘルムの目が笑っていなかったし、戦争の序盤でビルヘルムと同じ所で戦っていたアルゼンは、ビルヘルムがどんな奴なのかを観察し続け、その表情を読み取れるようになっていました。
それは、ビルヘルムが兵士たちと起こす問題に自分が巻き込まれないようにするためのものだったが、まさに今、問題が起こりそうな雰囲気だった。アルゼンは主人に危険を伝えるために目配せするがフェルナンには全く伝わりませんでした。
「取引をしに来ました」
「やっぱりグレンシアの方が良かった?俺の妹は本当に綺麗だよ!」
「あなたの妹には興味ありません。そしてグレンシアに帰属するつもりもありません。グレンシアの目的は知っています。叶えてあげましょう」
アルゼンが止める前に、ビルヘルムは言葉を放った。
「ただし、あなたが俺の下に入ることが条件です」
5.嵐と雷
北部での戦争は毎年約2ヶ月間行われます。野蛮族は飢えてグレンシアの領地に侵入し、グレンシア領主は食糧倉庫を明け渡す。
徴収された兵士は命をかけて戦うわけではないので、グレンシアの兵士だけでは野蛮族を一掃することができない。だからこそ食糧倉庫を渡すのは、お互い無駄な血を流させないための野蛮族との間の暗黙のルールでしたが、ビルヘルムが大族長の息子を殺してしまって、状況は一変しました。それまでからかうくらいだった野蛮族は、死にものぐるいで襲うようになった。
戦争において重要人物を殺さず捉えるのは基本で、それは捕虜交換や交渉の材料になるからです。しかし、ビルヘルムは自分の剣を奪ったからと言って、大族長の息子を殺してしまった。汚いやつが汚い手で自分の剣を触ったのが許せないのだとビルヘルムは主張しました。
ビルヘルムは斧と剣を振り回して戦うけれど、その腰には常にもう一本剣が下げられていました。リンケ侯爵の剣。確かに支給される剣よりはるかに質の良いものでしたが、ビルヘルムはそれを戦場で使うことはありませんでした。
そうして戦争は激化し、訓練所にいた徴収兵も戦争に参加することになった。ビルヘルムは前線を任され、やがて兵士たちから英雄視されるようになった。しかし、多くの兵士や騎士が、ビルヘルムは時折狂人のような振る舞いをすることを察していました。
首都では戦争とは関係ないかのように盛大な結婚式が行われ、カナリア公女が皇太子妃になりました。三日間花とパンが撒かれたという兵士たちの無駄話は、やがて廃妃となったラインハルト・リンケの話になった。
離婚して欲しいと言う言葉に激昂して皇太子の足を刺した女。新しく嫁げばいいのに、しかし顔は綺麗だという。ありふれた無駄話のはずでした。
しかし、その話をしていた兵士の首に、ビルヘルムが剣を突き刺し、もう一人話に交じっていた兵士の鼻を削ぎ落としました。
ディートリッヒによってビルヘルムは止められ、その後聴聞会が開かれたが、死んだ者と鼻を削がれた者は「皇帝と皇太子の悪口を言ったため処罰した」というのがビルヘルムの言い分でした。
結局鼻を削がれた兵士は慰労金が一切受け取れないまま帰されました。それからもビルヘルムは廃妃の悪口を言った者を斬った。そのビルヘルムの異様さを、アルゼンは間近で見ていました。
毎年起きる戦争のためにグレンシアは1万の私兵を許されています。けど、戦争が終わってしまったので1万の私兵を持つ領主は帝国にとって驚異でしかないので、兵士の規模を縮小、もしくは解体させることを皇帝は命じられるでしょう。
帝国には双璧と呼ばれる老将がいた。それがリンケ侯爵とグレンシア辺境伯。しかしリンケ侯爵が死んでしまったので、グレンシア辺境伯に匹敵する駒を皇帝は持っていなかった。だからこそグレンシアには兵士の縮小ではなく解散を求める可能性の方が高く、解散してしまっては行き場をなくした兵士達が盗賊に変わる可能性も、自分の身の危険も高まる可能性もありました。
だからこそグレンシアは優秀な騎士をスカウトしていました。一番スカウトしたかったのはディートリッヒでしたが、死んでしまったので次にスカウトするべき目的がビルヘルムになっていました。
1万の私兵が解体された後、自分の身と領地を守るためにグレンシアは優秀な騎士を求めているという話ですね。
ラインハルトが目を覚ますとベッドにパンが置かれていました。誰が置いたのかは明白だったので、もう少年じゃなくなったのに変わらず日課を行うビルヘルムをラインハルトは可愛く思いました。
ラインハルトはそのままディートリッヒがいない今、どうやって復讐を遂げればいいのか分からなくなり悩んでいると、部屋にビルヘルムがいることに気がつきます。
「……ビルヘルム、出て行ったんじゃないの?」
「出ていこうとしたら目を覚ましたんです」
ビルヘルムはラインハルトの傍まで歩き、跪いてラインハルトの手の甲に口付けます。その流れるような動作はまるで見知らぬ男のようにラインハルトは感じました。
ビルヘルムはペルナハ達が昨夜帰ったことを報告し、ラインハルトの手の甲に自分の頬を擦りながら「土地は好きですか?」と聞きました。
「どうして?私にくれるの?」
その時の会話は、子供が親に「将来お金持ちになったらお母さんに贅沢させてあげる!」と語るのと同じものだとラインハルトは思っていました。しかし、そうではなかったことに、ラインハルトはすぐ気づくことになります。
ビルヘルムはグレンシアの状況をよく理解していました。だからこそ、ビルヘルムはグレンシアは私兵をルーデンに貸すよう提案しました。私兵を得たルーデンは領地拡大して、帝国の二つの双璧を作ると共に、グレンシアは強い味方を得ることになる。そのために、ビルヘルムはルーデンの下にある雄大な領地オリエントを攻めて領土拡大を図るつもりでした。
「何を根拠に信じろと?」
「6ヶ月後に結果が出せなければ、俺は一生グレンシアの犬になる」
皇帝から解散命令が下されるくらいなら、あらかじめ他の領地に兵士を貸すというのは、グレンシア辺境伯も考えていたことでした。そうして夜に二人は帰り、その一ヶ月後。ルーデンに千人余りの兵士がやってきました。
ラインハルトはビルヘルムを捕まえて問いただすが、「ディートリッヒがもしこれほどの兵士を連れてきたら喜んでいたのでは?」と聞かれ、ラインハルトは固まってしまいました。ビルヘルムはラインハルトがミシェルを憎んでいることを知っていました。なぜなら、ラインハルトが歯軋りしながらミシェルの名前を呼んでいたから。
「ミシェル・アランカスは俺たちからディートリヒさえも奪っていきました。 もう憎しみはあなただけのものではありません」
ラインハルトはまさか復讐のことをビルヘルムが知っているとは思っていなかったので驚きました。
「あなたはどうせ俺を道具に使うでしょ。それなら俺が何をしても、それはあなたの能力で、あなたの怒りだ。俺はあなたの嵐か雷、稲妻になります。あなたの行く道を先に作るだけ。俺が作る道が気に入ってくれたら嬉しいです」
子供の成長を喜ぶべきなのかもしれないが、ラインハルトは単純に喜べなかった。子犬がライオンに育ったら、人を殺すのに十分な猛獣に育ったら、「よく育った」と褒めるだろうか、と思いました。
「もし……」
「……?」
男は彼女を振り返った。
「もしそれが気に入ったら、その時」
「………」
「その時、欲しいものを伝えます」
領地戦を宣言したルーデンの領主のことを周りは「廃妃が狂った」と言ったけど、結局ルーデンは冬を超える前に6つの領土を得ていました。東部のオリエント、デルマリル、パラ、それらの有力な領主はすぐにルーデンに跪くことになり、ルーデンの騎士は「ルーデンの狂犬」と呼ばれるようになり、やがてその異名は「ルーデンの雷」へと変わった。
皇帝は強大になったルーデンに頭を悩ませました。今のルーデンに匹敵するのはグレンシアしかいないが、グレンシアの私兵がルーデンに流れているので、グレンシアとルーデンは結託している可能性が高く、下手に手を出せないでいた。
そこへ、マレー伯爵がルーデンの騎士は、本来は兵士だったが徴収人数を減らすためにナダンティンに貸した略式叙任だけ行った騎士なのだと説明します。
マレー伯爵はラインハルトを首都に呼び、そこでリンケ侯爵家を復権させ、騎士を正式叙任させてはどうかと提案しました。何より名誉を重んじるのが貴族なので、それだけ与えれば不満が収まり、あとはよく口説いてうまくこちらが動かせば良いという話でした。
「それでは私の体面はどうなりますか」
状況も把握出来ず不満を唱えたミシェルに、皇帝は怒りを覚えました。
「皇太子の体面より重要なことは帝国にいくらでもある」
「……しかし」
「皇太子はグレンシア辺境伯とルーデン領土が結託して、1万を超える兵士が帝都まで来ても体面を保ちながら威張るのか!」
皇帝はミシェルの後ろに立っている侍従を見ました。ミシェルは片足が動かなくなったが、それでももう1つ足があるし、杖もある。しかしミシェルは歩くことをやめ、侍従に抱かれて移動するようになってしまった。静かだった皇太子妃が自分の父親が死んだからと言って皇太子を刺すはずがないと皇帝は考えました。
翌日、マレー伯爵からルーデンに、大領主への昇格とリンケ侯爵の遺体返還についての手紙が送られてきました。それはリンケ侯爵家の復権を示唆するものであり、かわりにルーデン領主と騎士は首都に来て皇帝に謁見し、騎士は正式叙任を受けることを求められ、ラインハルトは応じることになりました。
水晶門はアランカスで取れる水晶から作られており、水晶が持つ共鳴力によって、通過するものを希望の場所へと導いてくれます。通過するには共鳴用の水晶が必要なため、ラインハルトに水晶門を通るための水晶を渡されました。透明な水晶は真ん中に金属製のチップが入っており、一度使ったら壊れるようになっています。
門をくぐる前に、ラインハルトはサラ婦人に挨拶をしました。繰り返された領地戦では、降伏しなかった者の首ははねられ、降伏した者はサラ婦人の指揮下に入りました。サラ婦人は管理する領地が増え、眠れない日々が続いているようだった。
「婦人、ごめんなさい。できるだけ早く帰ってくるから」
「領主様、5年前。私はあなたが領地に来たばかりのことを覚えています。あの時、領主様が来て嬉しかったと嘘をつくつもりはありません。皇室の最も高貴だった方に、どうやって接したらいいかわかりませんでしたから。でも領主様を嫌ったことは1度もありません」
「婦人、いきなり……」
「領主様が時々、怒りを帯びた目で膝を見下ろしている時があるのを知っています。その怒りが消えるなら、何年でも首都にいても大丈夫です。ですから、できるだけゆっくり。余裕を持って、やるべきことを終え、栄光を抱いて帰ってきてください」
「……婦人、ありがとう」
サラ婦人の言葉に感激したラインハルトはそれだけしか言葉を出せなかった。ラインハルトの膝にはミシェルを刺したあと入れられた監獄で膝に受けた傷が色濃く残っています。励ましの言葉を終えたあとサラ婦人は帰り、マルクは侍女兼護衛として一緒に首都に行くことになりました。
マルクはビルヘルムの剣につけた青い布を見つけ、ラインハルトもそれが自分のものだと気づきました。
「それ、私があげたもの?」
ビルヘルムにこうして話しかけるのはとても久しぶりだった。ビルヘルムは遠征に行き、ラインハルトはその勝利報告を聞くだけだった。ラインハルトの知らないところで勝手に進む復讐。ビルヘルムは「俺たちの復讐」と言っていたけれど、ラインハルトは自分のものであるとは思えませんでした。そうした不安があったけれど、布を見るとラインハルトは緊張が解けました。
「見せて」
「……汚いです」
ラインハルトはそこで久しぶりに笑った。ラインハルトの笑顔を見たビルヘルムはどもりつつ「血、血もついているし…」と言いますが、ラインハルトは「大丈夫」と言って剣を奪い、巻かれている布を見て、剣は返さなくていいと話しました。
「あげるんじゃないよ、ただ…」
ラインハルトはビルヘルムを見上げ、その胸に手を置きました。ビルヘルムがわずかに反応したが、ラインハルトは構わず「首都は危ないと思う」と言って、ビルヘルムが持っていた水晶を自分が持ち、「どう言えばいいのかわからないけど、多分あなたはこれがなくても水晶門を通れると思う」と話します。水晶門は通常、共鳴用の水晶が必要ですが、元々は初代皇帝が作ったものなので皇室の一員なら誰でも水晶無しに通ることが出来ます。
「ビルヘルム、戻ってきて」
「……ライン?」
「他の言葉はいらない。私にはあなたが必要なの。あなたが首都で何になりたいと思っても、どんなことをしても構わない。私の元を去るとしても。でもその剣がある限り戻ってきて。それが嫌なら剣を返して」
ビルヘルムは「必ず戻ってきます」と返答しました。
「だからこれは俺にください」
剣を持つラインハルトの上にビルヘルムの手が重なり、耳元でビルヘルムが「ありがとう」と囁いて低く笑うので、ラインハルトの耳は熱くなった。
ビルヘルムは「俺も言いたいことがあります」と切り出し、水晶門のことを知っていたと話しました。
「いつから?」
「それはまだ言えません」
それはビルヘルムが皇帝の私生児であることを知っているということだった。最初から?それとも途中でビルヘルムを知っている人に教えられたのか?ラインハルトは困惑したけれど、ビルヘルムはやけに落ち着いた様子でした。まるでラインハルトが困惑するのを知っていたかのように。
そこへ、アルゼンがやってきた。元々はペルナハの副官だが、今はビルヘルムの副官になっていました。そして、ラインハルトはなぜグレンシア辺境伯が何の対価もなくビルヘルムに私兵を貸したのかを理解しました。自分の血筋を明かしたからだ。
一体どこまで考えて行動していたのかとラインハルトが考えていると、ビルヘルムが思い出したかのようにまた囁きます。
「あ、ライン。俺はまだ報酬について話していませんでしたよね?あなたの言う通り戻ってきたし、これからも生きて戻ってくるので報酬をください」
ラインハルトはその要求が決して断れないものだと知っていた。自分で耐えられない借金をした人は相手に何でも差し出さなくてはならないから。
「あなたです」
「私?」
「はい、ライン」
少し前より熱くなったラインハルトの耳元に低い声が舞い降りた。
「あなたを愛しています、ライン」
漠然としては感じていたが、ただ一度も具体的に考えたことのないことがあった。 ビルヘルムが自分に投げかける視線に向き合う度にラインハルトが感じた不安や恐ろしさ、あるいは暖かさのようなもの。それらがちょうど、愛という名を帯びて彼女にそっくり投げられた。
6.再会
ドルネシアは、小さな島々が集まるカナリア公国の8番目の公女で、12歳の頃に帝国に人質としてやってきた。ドルネシアという名前を呼ばれたことはそこから10年無く、だからといって、名前が呼ばれたから恋に落ちることもない。ただ従順で、それがドルネシアの命を繋ぎ、皇太子妃にもなることができました。
ドルネシアはミシェルに名前を呼ばれ、お香でも炊くか尋ねるが、それよりも足を拭いてくれと言われたので、まるで侍女のように怪我をした足を冷たい水で拭きました。
ラインハルトについての悪口を言うミシェルの話をそのまま跪いたまま聞き、ミシェルが大粒のサファイアのネックレスとイヤリングを送ったタイミングで、ドルネシアは侍女に助け起こされます。それを身につけて本来参加するはずのない謁見式に来るように言われ、戸惑っているドルネシアの様子を察して、侍女達がミシェルやドルネシアを褒めたたえました。口下手なドルネシアのかわりに、侍女達はミシェルの機嫌をとるのが上手かった。
皇帝はドルネシアのことを目の前で「皇太子妃」と呼んだことはなかった。ミシェルの片足と交換したようなものなので、それも当然かもしれないとドルネシアは思いました。
そうして迎えた謁見式。皇帝の許可を得て、マレー伯爵とその後ろにラインハルトが続いた。ラインハルトは皇太子妃時代とは様子が違い、繊細に編まれていた髪は、今では適当に背中で結ばれていました。
ドルネシアは、ラインハルトに対して複雑な感情を持っていました。自分のせいで父親も地位も失って、申し訳ない気持ちと、彼女を追い払うしかなかった自分のエゴ、そして勝利感。
ドルネシアは自分の父親から無味無臭の毒薬を渡されていました。公国に不利益がある場合は潔く死ねと言う意味でした。だからこそ、自分の宮に来た見知らぬ男が皇太子と知りつつも名前を教え、微笑むしかなかったと、仕方ないことなのだと自分に言い聞かせてきました。
謁見式は本来、皇帝に謁見するための華やかな場です。だからこそミシェルもドルネシアを飾りたてましたが、ラインハルトは全身真っ黒な出で立ちで、それはリンケ侯爵の死を想起させる行いだった。
マレー伯爵は皇帝への挨拶でラインハルトのことを「ラインハルト・デルフィーナ・ペールドン」と、わざとリンケの名前を使わずに紹介しましたが、ラインハルトは微動だにしなかった。
しかし、その次に紹介されたビルヘルムを見て、ドルネシアはもうラインハルトを気に止めることができませんでした。ビルヘルムは挨拶をして皇帝、ミシェル、そしてドルネシアを見た。その視線がドルネシアに向いた時、ドルネシアは自分の鼓動が早くなるのを感じました。そして自分を見て微笑むその顔を見て、ドルネシアはこれが自分の人生に訪れた初恋だと実感しました。
最初から悲劇の初恋が始まってしまいましたね…。
ラインハルトは謁見式を行うためのアマリリスホールに足を踏み入れる時、その大理石を踏みしめる音を聞いて、前回から合わせて20年以上の日々のことを思い出しました。遠くにいるのは、憎んでやまない男。今すぐにでもその顔を殴りに行きたかったけれど、ラインハルトが手で握りしめている水晶が、効果的に心を落ち着かせてくれました。その水晶はビルヘルムに支給されたものでしたが、ビルヘルムには必要なかったのでラインハルトが持っていました。
ラインハルトはミシェルをあえて見なかった。横目だけで十分で、憎悪を隠すことなくラインハルトを見ている様子を見て、ラインハルトは大笑いして「あなたも地獄に落ちた気分はどう?」と聞きたいくらいでした。憎しみから抜け出せずに人生を送る苦しみは、ラインハルトが誰よりも知っていました。
皇帝はビルヘルムの年齢を尋ね、ビルヘルムが「今年20歳になります」と答え、「若いのによく戦う」と褒められると「全て主君のおかげです」と返します。
そうしてラインハルトに向けられた皇帝の目は、衝撃と好奇心、疑問が浮かんでいました。ラインハルトは話を続けながら自分の手の中にある水晶を意識します。
2日後には新しい大領主を祝う宴会が開かれるため、そこに二人とも参加するように皇帝は命じ、ラインハルトを午後のティータイムに誘いました。
部屋に戻ったラインハルトは悩みがたくさんあったけれど、マルクとビルヘルム以外はルーデンの騎士といっても知らない者ばかりだったので気が抜けなかった。しかし、そんなラインハルトのためにビルヘルムは侍従長に部屋を用意させ、部屋に二人きりになるとようやく椅子に腰を落ち着けて座ることが出来ました。
ビルヘルムはラインハルトの足元に座り、まるで飼われた犬みたいだとラインハルトは思いました。この後に控えているティータイムで、皇帝は何を言うのか、要求するのか、ラインハルトにとってそれが悩みの種でした。のんびりした性格の皇帝が、急いで開いたティータイムで、もしかしたらビルヘルムの出自を確認するかもしれない。
ビルヘルムはラインハルトの手の甲に口付けし、その手のひらに頬を擦りながら「俺を息子にするのでしょうか?」とラインハルトに聞きます。
ラインハルトは、ビルヘルムは皇帝にラインハルトのことを「主人」と言ったので、皇帝はビルヘルムの出自についてラインハルトは知らないと思うはずだと答えました。だから皇帝はそっと顔色を伺って、自分だけで確認するつもりだろうと。
「……それではどうしましょうか、ライン」
「あなたはどうしたいの?皇太子になりたいの?」
足が不自由なミシェルと、小さな領地を大領地にしたビルヘルムなら、後者の方がずっと目立つだろうとラインハルトが考えていると、「難しいので俺にはよく分かりません」とビルヘルムはとぼけました。
「ただあなたが今俺の額に口付けをしてくれたらと思っています。知っておいてください、ライン。俺にはあなた以外何も必要ありません」
は〜〜〜〜〜
ぐいぐい来るけど、可愛い犬ですアピールがずるいんですよね…
ティータイムでは皇帝がラインハルトを「リンケ卿」と呼び、リンケ侯爵家が復権されることを明確にしました。そしてビルヘルムの正式叙任のための出自確認も行われることになり、ラインハルトは皇帝にこっこり水晶を渡します。
ビルヘルムの母親がコルーナであると結婚証明証から証明され、帰属名簿からコルーナを復権させることが告げられました。
リンケ侯爵邸は皇太子に慰謝料として引き渡されていたため、ラインハルトは皇居に留まることになりました。与えられた歓迎宮に入り、マルクに宴会のために適当な服を用意するよう命じると、マルクはビルヘルムが宴会のためにドレスを用意したのだと報告します。
ラインハルトはそれを聞いてすぐビルヘルムを呼び出し問い詰めると、「サラ婦人が宴会用の服装がないと言っていました」と話しました。ラインハルトはそれだけでは納得できず、マルクに部屋を出ていくように言ったが、それをビルヘルムが止めます。
「皇居には敵が多いです。男と夜に同じ部屋で二人きりでいると悪い噂が立ちます」
ラインハルトはそれがビルヘルムが逃げようとする時の手段なのだと理解していました。積極的に求愛するくせに、重要なことは少しも話さず逃げる。
「ビルヘルム、私を笑わせようとしたのなら、その冗談は成功したことにしてあげる」
「笑っていませんが」
ラインハルトは元々悪い噂は立っていたし、それは皇太子妃時代からある事なので慣れていることを話しました。また、人々は既にラインハルトとビルヘルムの関係を勘ぐっているので意味がないこと、噂が立ったとしても当人が堂々としていれば問題ないことを続けて言いました。
「私は数年前までは痩せたあなたを自分で洗っていたわ。生意気に男だなんて。そんなこと絶対ないのに。あなたは私の子供に違いないのだから逃げようとしないでドアを閉めて入ってきなさい」
それはビルヘルムに対する宣戦布告だった。ビルヘルムは眉をひそめ、マルクはそんなビルヘルムを見て笑いました。
「ルーデンの雷が領主様の前では赤ちゃんみたいですね」
マルクはそう言ってビルヘルムを部屋に押し込んで扉を閉めて出ていった。ビルヘルムは笑っているラインハルトの元に歩み寄り、ラインハルトがいるベッドに膝を乗せて押し倒しました。
「これでも子供に見えますか?」
ビルヘルムは意地の悪い笑みを浮かべていたが、ラインハルトはベッドの上で更に笑った。ラインハルトも子供の時、父親が「小さなアップルパイ」と呼んでいたことが恥ずかしがった。ルーデンを大領地にした「ルーデンの雷」が、子供の頃の話をされて自尊心が傷つかないはずがありません。
ラインハルトは「私が軽率だったわ」と言うと、ビルヘルムはそうではないと言います。
「あなたと俺は8歳しか差がありません」
「そうだね」
「8歳の時に子供を産むことは出来ないじゃないですか」
ビルヘルムは普通の子供としての人生が歩めなかったから、唯一体温を与えてくれたラインハルトを初恋の相手に選んでしまったのだと思っていました。
「もし、出会い方が違ったのなら私はあなたを好きになっていたかも」
それほど魅力的な青年だったし、おそらく多くの女性がビルヘルムを見て恋に落ちるだろう。数年後には恐ろしいほどに色情的な男に育つはず。ラインハルトはビルヘルムの頬を撫で、「でもビルヘルム」と言葉を続けました。
「それじゃあ弟にしよう」
「……ライン」
「私の誇らしい弟」
ラインハルトはビルヘルムの心に答えることはしないと決めていました。本来初恋は実らないと言うし、ビルヘルムはラインハルトの傍に必要だけど、それは恋人としてではない。もちろんビルヘルムに魅力を感じていない訳ではなかったが、それより外の事情が複雑だった。仮に恋人になったとして、下手なことをして関係が悪化すれば、痛手を負うのはラインハルトです。
ラインハルトは愛というものを信じていなかった。
ラインハルトは「いつ、どうやって知ったの?」と、彼が自分の出自についてどうやって知ったのか知りたくてビルヘルムに尋ねますが、「まだ言えない」とビルヘルムは答えました。
「……それが気になりますか?」
ラインハルトは、自分にとってビルヘルムは子供で、親は子供のことを知りたがるものだと話しました。
ラインハルトは皇帝と交渉をする前にその事を知っておいた方がいいと思い、それを説明しようしたけれど、不機嫌になったビルヘルムは「子供は隠した秘密を親にいちいち聞かれるのがあまり好きではありません」といって、荒々しく扉を閉めて部屋を出ていってしまいました。
部屋を出たビルヘルムはそのまま待機していた騎士に「周りを見てくる」と行って外に出ました。マルクがビルヘルムを追いかけ、ビルヘルムを宥めるためにラインハルトが宴会でビルヘルムには特別良いものを選べと言っていたと話します。実際のラインハルトはそんなことを命じていないし、むしろ「適当に」と言っていたが、マルクはビルヘルムがラインハルトを愛していることを知っていたから、彼女がビルヘルムに対して心を配っていることを伝えたかったし、二人には上手くいって欲しいとも思っていました。
マルクは3年間、ビルヘルムを戦地でよく見てきました。ディートリッヒを失った今、ビルヘルムの心の拠り所が無くなることをマルクは恐れていたのです。
「……閣下がですか?」
顰め面が解けたのを見て、マルクが「はい、気を遣うようにと言われました」と言うと、ビルヘルムは素直に「わかりました」と答え、マルクはやはり大人しくて純粋なのだと思いました。
そこから話はラインハルトの元夫の話になり、「男を見る目がない」とビルヘルムが言うので、マルクは「他にも皇子がいたら選べるけど、一人しかいないから選べなかったのでしょう」と話しました。
それにラインハルトの結婚相手は父親であるリンケ侯爵が選んだのだと話すと、「女性にとって最高の男は皇帝の息子ですか?」とビルヘルムに聞かれ、マルクは「本当は皇帝だけど、おじいさんだから。犬でさえ血統の良い方が高く売れる」と話すとビルヘルムは笑ってからその場を立ち去りました。
ビルヘルムはそのまま庭を進み、白い東屋に入って座り、長いため息をついた。
「あの時、ああすべきではなかったんだろうか」
ビルヘルムは呟いた後、剣に視線を落として、巻かれた布を乱暴に剥ぎ取った。それはまるで憎い敵の皮膚を剥がすような荒々しい動作でしたが、布を解くとそれを睨みつけ、また剣に結び直します。
「………」
愛する相手を押してみても、まるで大きな壁に阻まれているようで、ビルヘルムは悔しかった。
その時音がして、ドルネシアが現れました。侍女がビルヘルムに向かって皇太子妃に礼を取れと言い、ビルヘルムは皇族に対する一番簡単な礼を取り、名前を名乗ります。
ドルネシアは前皇太子妃を廃妃にした悪女だと噂されが、自分を見た人々がその印象を好感に変える瞬間を多く見てきました。だからこそ、ビルヘルムも自分に好感を抱くのだと思っていたけれど、ドルネシアの予想に反して、ビルヘルムの目は淡々として冷たかった。
昼間に見た、ドルネシアをその黒い瞳に入れて笑ってくれたら、そしてそれを永遠に見ていたいという欲求が溢れました。
ドルネシアは自分の宮がここから近いため、この時間はこうして散歩するので申し訳ないがこの時間だけは譲って欲しいとビルヘルムに頼みます。ビルヘルムが何も答えなかったので肩を竦め、怒る侍女達を宥めて立ち去ると、それまで黙っていたビルヘルムは笑いました。
「その必要はありません、妃殿下」
ビルヘルムはドルネシアが立ち去った後に彼女が落としたハンカチを拾い上げました。
誰かの予想が見事に合致した夜だった。
1巻後編を読んだ感想
2巻から復讐が大きく動いていくことになります。ビルヘルムの初恋の行方についても動きがあります。
▼1巻をリアルタイムで読了したときの私の感想です。
🐕🦺1巻読み終わりました
子犬だと思ってヨシヨシ育ててたら実は全然犬じゃないけど…?ってなってるヒロインと、害はありませんし従順です🥺って思わせつつヒロインを手に入れるために計画を練ってるドス黒年下ヒーローの話でした
2巻も楽しみです— いり☂︎ (@Share_Book39) July 23, 2023
次回の更新はtwitterにてお知らせします!