コミカライズ連載している「元夫の番犬を手なずけた」の韓国原作小説を読んだのでネタバレ感想を書いていきます。韓国語は不慣れなので翻訳が間違っていることもあります。
(間違っているところを見つけた場合はtwitterのDMでコッソリ教えてください…)
元夫の番犬を手なずけた(전남편의 미친개를 길들였다)
原作:Jkyum

7.取引
アルゼンへの頼み
宴会当日。ビルヘルムはここ2日間ラインハルトを避けていて、ラインハルトも彼を慰める事はできないのであえて呼ばなかった。
ラインハルトはここまで早い段階で皇帝の私生児という切り札を使うつもりではありませんでした。狙うのは今の皇帝ではなく、ミシェルが皇帝になった時でしたが、ビルヘルムが先にグレンシアと交渉してしまったのでラインハルトの計画は全て崩れてしまいました。
ラインハルトはアルゼンを呼び出し、ルーデンを強固にするためにとある人を探して欲しいと頼むと、アルゼンは「私の上官がペルナハ・グレンシアだというのはご存知ですか?」と尋ねました。グレンシアに報告するという露骨な態度だったので、ラインハルトは「好きにしなさい」と答えます。
「あなたの上がグレンシアのキツネであれ、皇帝であれ、私の知ったことではない」
ラインハルトが探しているのは前回ヘルカの経営を行っていた男でした。父の死からすぐに抜け出せなかったラインハルトでしたが、彼がいたおかげでヘルカはめちゃくちゃにならずにすんでいました。今はまだ首都にいるはずなので、男にルーデンの経営を任せようとラインハルトは考えていました。
アルゼンを選んだのは、首都に慣れた人がいないという理由もあったけど、それよりペルナハの好奇心を引き寄せたかったからです。グレンシアはビルヘルムが居なくなってしまえばルーデンから手を引いてしまいます。しかし、広大になったルーデンの管理を任せる人材として、廃妃が突然首都から男を連れてきたら。そしてそれが優秀だったら。興味を引かれるはずです。
ラインハルトはこの2日間で自分からビルヘルムが離れていった時のことも考えていました。愛を信じていなかったし、変わるものだと思っていたから。
ペルナハがグレンシアの人間であることを周りには隠していました。しかし、宴会では流石に知り合いに会う可能性があったので、アルゼンは一旦護衛任務から抜けており、その間にラインハルトは仕事を頼みました。
ビルヘルムの嫉妬
ビルヘルムはこの2日間ラインハルトを避けてきたけど、今日はリンケ侯爵家が復権する日です。ラインハルトの宴会とも言えるのでそんな態度を続ける訳にはいきませんでした。
しかし、会いには行きにくくて、結局ビルヘルムはマルクがラインハルトに届けるための宝石箱を自分が持っていくという事で、何とかラインハルトの部屋を訪れます。
しかし、アルゼンがラインハルトの部屋から出てきたのを見て、ビルヘルムは嫉妬しました。ビルヘルムの顔はさらに険悪になり、アルゼンを置いて部屋に入りました。
応接間ではバスタブが設置され、湯浴みをするための準備が急いで行われていました。その奥のラインハルトの部屋に入った時、「ディートリッヒ」と名前を呼んで嘆くラインハルトの声を聞いて、ビルヘルムの顔はさらに鋭くなった。ディートリッヒは常にビルヘルムの前に立ちはだかり、ビルヘルムに罪悪感と劣等感を抱かせます。
ビルヘルムがラインハルトの名前を呼ぶと、すぐにラインハルトは取り繕って「どうしたの」と聞きました。アルゼンにはどういう用事があったのか尋ねると、「ビルヘルム」と強く名前を呼ばれ、ビルヘルムは目を逸らします。
ビルヘルムがアルゼンと二人きりになるのは良くないことだと話すと、ラインハルトは「あなたが上官みたいね?」と言いました。
「いえ、ただ…」
「そこの扉を閉めて」
丁度入ってきた侍従に命じて扉を閉めさせ、ラインハルトは「皇子になりたいのなら今からでも言って。皇子殿下と呼びますから」とイライラしながら言いました。
「……違います」
ラインハルトはビルヘルムに近づき、ビルヘルムが胸につけていたルーデンの紋章を掴んで外します。
「私の一挙手一投足に口出ししたいなら、皇子殿下として接しましょう。ただし私の夫でなければ、家族でもなくなる事は知っておいてください」
敬語で話し始めるラインハルトを見たビルヘルムは困惑しました。
ラインハルトが提示する選択
「私はミシェル・アランカスを殺すために全力を尽くした。本当にたくさんの時間を……一人で、寂しく過ごした」
「……あなたのそばにはディートリッヒがいたでしょう。それから俺も」
「いいえ、ビルヘルム。私は本当に多くの時間一人だった。私の言うことが信じられない?」
「いいえ、信じます。そしてあなたが一人で過ごした歳月も知っています」
ビルヘルムの言葉は同情を買おうとしているのか信頼を得ようとしているのか分からなかったけど、ラインハルトは構わず「ところで、どうしてあなたは信じさせてくれないの?」と畳み掛けます。
「あなたが私を愛しているという言葉も私は信じられない。秘密を明かすことも、素直に話すこともないのだから」
「あなたこそ俺に心をくれるつもりはないのでしょう」
ラインハルトはビルヘルムの前髪を払い、その眉にある傷を触りながら名前を呼んだ。
「あなたは近いうちに眩しいほど素敵な男になるわ。そうすればあなたも選択肢が増えるし、そして他に愛する人も現れる」
ビルヘルムはラインハルトの手のひらに自分の頬を擦り付け、「俺にはあなただけです」と言うけど、ラインハルトはそれはビルヘルムが会ったのがラインハルトだけだっただけで、それは愛では無いのだと話します。
「あなたは本気だと言うけれど、あなたは私を信じさせてくれる言葉は与えてくれないじゃない」
ラインハルトは「もっと正直になってみましょうか」と話しながら、頬を撫でていた手を首元まで下ろし、ビルヘルムのボタンを触って外し、胸板を優しく撫でました。真っ赤になるビルヘルムをそのままソファに押し倒します。
「あなたの中途半端な愛情を受け入れるのは、実はそんなに難しいことじゃないの」
ラインハルトはビルヘルムの体の上に乗り上げ、彼の唇と自分の唇が触れ合いそうな距離で止めた。
「人々が噂するようにあなたを毎日ベッドに引きずり込んで身を混ぜることもできる」
ビルヘルムは強くソファを掴み、衝動的にラインハルトを捕まえないように耐えました。
ラインハルトは自分の喪服のボタンを外し、胸にビルヘルムの手を導きつつ、自分の体が欲しいなら渡すが、そのかわり確実に復讐を遂げることを約束しなさいと話しました。
「私はあなたを失うわけにはいかないから、あなたが私の体を欲しがるなら差し出すしかない。でも私はあなたには体以外には渡さない。私と取引をするか、それとも今までのようでいるか、選択しなさい」
「……あなたの復讐が終われば、その時はあなたは俺を愛することができるでしょうか」
色々な欲と感情が入り乱れるビルヘルムの瞳を見ながら、ラインハルトは「それは断言できないわ」と言いました。
ビルヘルムはディートリッヒの名前を出し、ラインハルトにとって彼以上になれるのかと尋ねます。
「……そうなるかもしれない」
「断言はしてくれないんですね。俺はただあなたが愛してくれるかもしれないという可能性にしがみついて、今すぐ酔うことができる甘さを諦めなければならないのですか?」
「強要はしてないわ」
ビルヘルムは息を吐き出し、ラインハルトの首筋を撫でてから「ライン。俺には言えない事があります」と言います。
「けれど、俺はここであなたを諦めることで、信頼を差し出します。あなたの体をもらっても、俺の渇きが満たされるとは思えませんから…」
ビルヘルムは目付き変えて「ラインハルト」と名前を呼びました。
「愛しています。俺はあなたを得るためなら何でもします。だから俺を信じてください」
「……わかったわ」
ビルヘルムは息を吸って、ラインハルトの足を触った。ビルヘルムがラインハルトの腰から手を離せないまま未練がましく眺めているのを見て、ラインハルトはビルヘルムの顔を引き寄せ、その額に口付けを落としました。
この時、ビルヘルムのビルヘルム()の存在に気づいたラインハルトは、心臓の鼓動が速くなり、改めてビルヘルムが少年ではなく男であることを実感しました。
宴会
宴会に飾りひとつ付けずに行こうとするラインハルトに、ビルヘルムは宝石箱を渡しましたが、「私に何か与えたいのならミシェル・アランカスを生きたまま私の前に差し出しせばいい。それ以外はいらない」と言われてしまい、代わりにビルヘルムは「エスコートさせてください」と申し出ます。
「ビルヘルム、あえてそこに許可が必要だなんて思わなかったわ」
「ラインハルト。俺はあなたの許可なしには何もしません。本当ですよ」
そうして出席した宴会では、真っ黒で装飾を何もつけていないラインハルトのことを見て、人々は驚き、みすぼらしいと囁きました。しかし、ラインハルトは自分に挨拶をした人々に余裕を持った対応を見せるので、裕福だからあえて見せびらかす事はしていないのだと周りは考えを変えました。
皇族が入場し、皇帝は三度目の大領地誕生を祝いました。その次にビルヘルムの正式叙任も行われたが、人々の中で喜べない者がいた。三男だった皇帝を今の地位に押し上げ、ミシェルの母でもあるカストレヤ皇后だった。
ビルヘルムを見たカストレヤ皇后は、その容姿が若い頃の皇帝に似ている事に気がつきました。さらに男の家の名前が「コルーナ」だというのを聞いて、確信に変わります。
愛している夫にこのような辱めをされると思っていなかったカストレヤ皇后は、ミシェルにこっそりと内情を知らせます。二人は1ヶ月首都に滞在するというラインハルトの話を聞き、対策を練ることになりました。
カストレヤ皇后は、自分が惚れたという理由で現在の皇帝を帝位に付かせた経緯があります。それほど深く愛していたため、気づくことができたのでしょう。
宴会に疲れてきたラインハルトはビルヘルムの腕をとり、外に抜け出します。そして侍従に案内されて皇城の隅の部屋に案内されると、先に宴会を退席していた皇帝が待っていました。
皇帝はラインハルトと挨拶を交わしたあと、ビルヘルムに向かって「私の息子」と話しかけました。皇帝は水晶を渡される前から、ビルヘルムを見て昔出会った女を思い出していました。荒れた肌やみすぼらしいドレスが目に入らないくらい、森の香りがする女だった。女は皇帝に目を向けなかったが、皇帝は愛してしまった。
皇帝がビルヘルムと話すのを眺めていると、ラインハルトは皇帝に名前を呼ばれました。
「私がもう一度君に皇子妃の冠を被せるのなら、受け入れるか」
皇帝はカストレヤ皇后によって帝位につきましたが、そんなつもりのなかった皇帝自身はそれを酷いと思っていたし、怖いとも思っていました。最初から破綻している夫婦関係ですね。
皇帝の算段
ラインハルトは自室に帰り、バスタブに腰かけながら深いため息を吐きました。皇帝は「私の息子が皇子になるのなら、その隣には君がいなくては」と言ったけど、ラインハルトが望んでいるのは皇子妃の冠ではありません。そのことをもちろん皇帝もわかっているだろうし、こちらを探るための言葉だったのだろうけど、ビルヘルムの反応を見て、皇帝はその言葉を実現させるのだろうとラインハルトは思いました。
ラインハルトはその場で直ぐに「望んでいません」と答えましたが、皇帝はすでにビルヘルムがラインハルトに執着しているのを把握し、さらにラインハルトの領地ルーデンにはビルヘルムが必要だと言うことも理解していました。
ビルヘルムを皇子にしてその妃にラインハルトを添えれば、3番目の大領地となったルーデンの牽制策はそれで打たれてしまいます。
また、皇太子妃ではなく皇子妃にしたのも理由があります。大領地の爵位は皇帝には帰属しないので、皇太子妃になるならルーデンは没収されてしまいます。しかし、皇子妃であるならラインハルトはそのままルーデンの大領主として続けていける。皇帝がしたのはそういった提案でした。
皇族と結婚して妃になると、妻の持っていたもの(領地)は基本的に夫の所有になります。しかし、皇帝にはそれが当てはまらないため、皇后のものは自動的に帝国に没収されてしまうルールのようです。皇帝のものは帝国のもの!って事ですね。
皇子となったビルヘルムと結婚する→ラインハルト(とビルヘルム)はルーデンの領主のまま。
皇太子になったビルヘルムと結婚する→ゆくゆくは皇帝と皇后なのでルーデンは二人の個人所有ではなく、帝国のものとなってしまう。
皇帝は「それなら何を望むのか」とラインハルトに問いかけつつも言葉を続けました。
「それよりもっと気になることがある」
「何でしょうか」
「足で十分かな?」
十分なはずがない、と瞬時にラインハルトは思いました。
「君は私の息子を刺した。ルーデンに追い出されたが、リンケ侯爵の遺体を返してもらったからもう満足しているのか?まさか養父の遺体一つのためにここまで来たわけではないだろう。大領主の地位を理解している君が、その地位を認めてもらいに来たわけでもないだろう」
「恐縮です」
「それなら君が望むものは何か。片足では満足できなくて帰ってきたのではないか」
「陛下の息子です」
「私がかつて愛した女を殺した女の息子でもある」
皇帝には父性愛がないのかと疑うほどの言葉でした。しかし、皇帝は元々ビルヘルムの存在を知る前から子供が二人いました。ひとつはアランカス帝国そのもので、皇帝はそれが何より大事でした。ビルヘルムという息子が増えて良い選択ができるのなら、ミシェルを切り捨てるのも厭わないのでしょう。
そして、皇帝はラインハルトを甘く見ていなかった。わずか5年でルーデンを大領地にしたその手腕を高く評価していたし、ビルヘルムを見つけた経緯も森で拾ったという流れなのも聞いていました。道端の石ころから私生児を見つけるには運が必要で、ラインハルトにはその運があると評価していました。
油断ならないグレンシアと、そこに新たに現れたルーデン。今はいいが、ミシェルが帝位についた時にきっとラインハルトによる内乱が起き、帝国は深手を負うはず。帝国を傷なく存続させるには、皇帝が取る選択肢は限られていました。父性愛が無いわけではなかったが、それはアランカス帝国に向けられていました。
「君は嫌いだが、取引の相手としては素晴らしい」
ラインハルトから見た皇帝は「のんびりや」というものと「古狸」という評価がありましたが、流石にこういった場面では古狸さが出てきますね。
ラインハルトはまだ仕事が残っていたことを思い出し、マルクにアルゼンを呼ぶように命じましたが、代わりに部屋に入ってきたのはビルヘルムでした。ビルヘルムはまだアルゼンが帰ってきていないことを知らせつつ、ラインハルトの服のボタンが2つほど外れている姿なのを指摘します。
「あいつにこんな姿を見せるつもりでしたか」
「私をそんな目で見る変な人間はあなただけだよ」
「あなたをそんな目で見ない人たちの方が変ですね。しかもバスタブの前だなんて」
そういうビルヘルムもバスタブの前に来ているではないかと指摘すると、「はい。そしてバスタブの前でボタンを外して座っているあなたを見ています」と話し、ラインハルトに顔を近づけます。
「20歳になったばかりの男に見せるには酷い光景だと思いませんか」
その話し方がディートリッヒを思い出させて、ラインハルトは笑いながら「自分がまるで30歳のように言うのね」と言いました。
「あなたについて行こうと思ったら早く大人にならなければなりませんから」
ビルヘルムはバスタブの中に少し湯を入れ、そこにラインハルトの足を入れて洗い始めます。ラインハルトが警戒して部屋の扉が空いているのを確認していると、ビルヘルムが「あなたの許可なしには何もしませんよ」と言い、洗い終わった足を拭いてラインハルトの膝に、布の上から口付けを落としました。
これは許可が必要な行為ではなく、ただ神に敬拝しただけだとビルヘルムが言い訳を言いました。ラインハルトは話を変えるために皇帝との話題を持ち出したくて「どう思う?」と尋ねますが、話題を理解していなかったビルヘルムは「美しくてうっとりします」と、違う答えが返しました。
「……私は皇帝が言ったことについて聞いているのだけど」
「感想は似ています。恍惚としました。あなたが俺の妻になるという話だったじゃないですか」
皇帝の話は鵜呑みにしないで、とラインハルトが言うと素直に「わかりました」とビルヘルムは答え、ラインハルトをベッドまで運んでマルクにバスタブを片付けさせました。
実はこの時ビルヘルムは皇帝を殺そうと思っていましたが、まさかそんなことを考えているなんて、ラインハルトは知りませんでした。
ビルヘルムの考え
ラインハルトが眠ったあと、ビルヘルムは庭に出ていました。ビルヘルムは皇帝がラインハルトに取引をもちかけた事を思い出し、皇帝を殺してしまいと思っていました。
ビルヘルムはラインハルトを誰かに与えられることを望んでいなかったし、もしそうなら既にラインハルトを押し倒しています。ビルヘルムが欲しいのはラインハルトの全て。
ラインハルトは信頼するものに笑いかける時、左頬にはえくぼができ、瞳が金色に輝く。そのような笑顔をビルヘルムも向けられたことがあるけど、それはペットを可愛がる種類のものでした。本当にその笑顔が向けられたのは、ディートリッヒにだけ。
ディートリッヒとラインハルトはお互いに目が合うと笑い合い、暖かい空気が漂った。その笑顔を自分に向けて欲しいとビルヘルムは願ってきました。
思案していたビルヘルムの元に、酔ったミシェルが大騒ぎしながら現れます。ミシェルは酔った勢いでこのままラインハルトと私生児であるビルヘルムを殺そうとしていました。いつもなら止めてくれる皇后も、今日ばかりは自分の宮に閉じこもってしまっています。
ドルネシアがどうにか落ちつけようとしていたけど、力に叶わず突き飛ばされ、ビルヘルムはその腰をつかんで支えました。皇太子妃に触ることの出来る男は皇太子だけだと決まっていたので、ミシェルは怒り狂い、剣を抜いてビルヘルムに突きつけます。
ドルネシアが止めようと叫んだが、その前にビルヘルムは剣を握るミシェルの手首を叩いて剣を離させ、ミシェルの首を打って気絶させました。
倒れないようミシェルを支え、ビルヘルムは侍従達にミシェルを渡します。ドルネシアが「一介の騎士としては非道でしたが、命を脅かされたのだからやむを得なかった事だと信じています」と言って、ミシェルを連れて立ち去りました。
ビルヘルムは立ち去るミシェルの後ろ姿を眺め、あのような不細工がラインハルトと同じベッドを使い、一時期だけでも彼女を独占していた事実を考え、やはりミシェルから殺すべきだと考えを改めました。
そんなことを考えているとドルネシアが振り向き、ビルヘルムと目が合った。変わっていないものもあるのか、と思いつつビルヘルムは目をそらすことなくドルネシアを眺めました。
ヘイツ・イェルター
アルゼンからラインハルトの目当ての男が来ていることを知らされ、ラインハルトは疲れた体を起こし、ガウンを羽織って男と会いました。ヘイツ・イェルターは、現れたラインハルトに挨拶をします。
前回の人生でヘイツは首都のアカデミーに通ったあと財務庁にいたが、兄が亡くなったためイェルター男爵家を継ぐためにヘルカに帰った。しかし、兄嫁が自分の腹にいる子供こそが跡継ぎだと主張し、家門を継げなかったヘイツは結局ヘルカ領地の末端書記官になり、ラインハルトがヘルツの能力を見出して重要な役を任せていました。
この頃はまだ兄も存命中で、ただ財務庁で評価もしてもらえず燻っているはずでした。
「ルーデンは小さかったから元々いる管理人では手に負えなくなっているの。そこで私の知り合いがあなたを推薦した」
「どなたですか?」
「それはあなたが管理人になった時に教える。ルーデンは今政治的にとても微妙な立場だから推薦人と私が親密なのだと広めたくない」
ラインハルトは、ヘイツが上司の代わりにオリエントの脱税調査を行っていることを知っていると話します。前回の記憶で、ヘイツは20年間オリエントから税金を徴収できたのは自分だけで、上司は評価してくれなかったと話していたのを覚えていました。
「私はあなたが一番望んでいるものを与えることが出来るわ」
「私の一番の望みを知っているのですか?」
「ヘイツ・イェルター。私はむやみに危険な領地の財務管理人として連れていく性格じゃない。そこで長くいる人ではないだろうし、5年間私のそばで働いてくれたら、その後は好きにすればいい」
「本当に私が何を望んでいるのかご存知なのですね」
ラインハルトは領地に自分が戻る際にヘイツを連れていくと話し、給料についても提示するとヘイツは頷きました。
ハンカチと手袋
ドルネシアは侍女達を下がらせ、皇太子宮を歩いていましたが、何かに躓き倒れ、柔らかいものの上に座り込みました。
「大丈夫ですか」
顔を上げると、そこにはビルヘルムがいました。木に寄りかかって座っていたビルヘルムの足に躓き、倒れたドルネシアは彼の足の上に座ってしまっていました。
ドルネシアは慌てて立ち上がろうとするけど中々立ち上がれず、ビルヘルムに助けられながらなんとか立ち上がりました。
本来ドルネシアは皇太子妃宮の庭にいるビルヘルムを問いただすべきでしたが、ビルヘルムは「まさか本当に会えるとは思いませんでした」と話し、ドルネシアにハンカチを渡します。それはドルネシアがわざと落としたハンカチだったけど、ドルネシアは勇気が出ず、あれ以来、歓迎宮の庭には行けていなかった。
「ありがとうございました。大事にしていたものなので…」
本当はハンカチなど豊富にあり、大事にしているものなど無かったけど、ドルネシアは自分の持つ静かで悲しい雰囲気が、自分の言葉の説得力を高めてくれることを知っていました。
「そうだと思いました」と答えたビルヘルムは再び座り、横にドルネシアを誘います。少し離れて座ったドルネシアだったけど、ビルヘルムの手が伸び、ドルネシアの足首を晒して怪我がないか確認しました。真っ赤になるドルネシアを見て「もしかして怪我をしたのかと。驚いたのなら申し訳ありません」とビルヘルムは謝りました。
ビルヘルムはドルネシアの腰を掴んで立たせてやり「送り届ける」と言いますが、それこそ問題になるのでドルネシアは頷けません。かわりにドルネシアは「少し足が痛いから話し相手になって欲しい」と頼みました。本当は全く足は痛くなかった。
「悪い噂が立つのでは」
「どうせ他人は私のことを悪く言うんです」
ビルヘルムは思わず苦笑いしました。これみよがしにハンカチを落とされたが、本当はドルネシアに会いに来るのがビルヘルムは嫌だった。そして彼女が言うその言葉は、数日前にラインハルトが言った言葉と似ていたけど、ドルネシアの言葉には吐き気を催しました。
ドルネシアに誘われて森の中に東屋があるという道を歩き始めましたが、ドルネシアはもちろん、ビルヘルムもその先に東屋がないことを知っていました。しばらく歩いてからドルネシアは「道を覚えたはずだけど違ったようです」と申し訳なさそうに言います。
ドルネシアは道を戻りながらビルヘルムに明日の予定を尋ね、ビルヘルムは先代リンケ侯爵の遺体返還のために公共墓地に行くのだと答えました。ドルネシアは「先代侯爵の死は本当に残念です」というので、その馬鹿馬鹿しい言葉に、ビルヘルムは大声で笑いたくなりました。
ビルヘルムはラインハルトについて考えました。仮にドルネシアをラインハルトの前に裸で連行し、突き出しても、ラインハルトはドルネシアの目玉をくり抜くことはせず、むしろ自分の外套を羽織らせるでしょう。非情になりきれず、暖かくて優しいから。だからこそ、非情なことは全てビルヘルムが行うのだと決心を固めました。
そうして森を抜ける時、ドルネシアが足を踏み外し、素早く支えたビルヘルムの首を抱きしめ、二人の距離が近づいた。ドルネシアは目を閉じ、口を少し開けたが、待っていた感触はいつまでも訪れないので目を開けると、顔を固くしたビルヘルムはドルネシアから離れ、「皇太子妃宮の庭園なので一人で帰れると信じています」と言って立ち去ってしまいました。
恥ずかしがり屋なのだとドルネシアは思い、ドキドキしながら帰り道を歩いているとビルヘルムがつけていた革の手袋が落ちていました。なぜ両方落ちているのかと想像しながら持ち帰ったけど、実は吐き気を催したビルヘルムが捨てたということを、ドルネシアは知りませんでした。
ラインハルトの肖像画
ラインハルトとビルヘルムは皇帝に誘われ、歴代皇帝の肖像画を眺めていました。初代皇帝であるアマリリスが恋人に書かせたという小さな肖像画には、見覚えのある金の指輪がはまっていました。
アマリリスには二つの宿願があり、一つは野蛮族の制圧と、もう一つは竜が眠ると言われている氷で覆われたフラン山脈の制圧でした。皇帝は一つの宿願が自分の息子によって実現できたことを喜んでいました。
ビルヘルムは皇帝の肖像画はどこにあるのか尋ね、皇帝は別の廻廊に案内しました。そこには皇帝とカストレヤ皇后、ミシェルの肖像画が飾られています。以前はそこに幼いラインハルトの肖像画もあったけれど、さすがに今はなかった。ビルヘルムがラインハルトの肖像画はどこにあるのかと聞くので、皇帝もラインハルトも困惑しました。
「ルーデンの城に飾ると良いと思った」とビルヘルムが話すので、皇帝は新しく画家を紹介すると話しました。それは以前の肖像画は捨てられたことを意味していました。
皇帝と別れたラインハルトはビルヘルムを叱責し、耳を軽く引っ張ります。侍従に休めるところがないかを聞くと、整備された遊歩道に案内されました。ラインハルトはそこを歩きながら、3週間後に開かれる大宗教会まで首都に滞在しなければならないことを話し、その理由がビルヘルムにあるので彼の手の甲をつねりました。
大宗教会とは、皇族や貴族たちが参加する大規模な宗教行事の事のようです。7日間にわたって行われ、それぞれの日に祈祷を行います。
その時、通り過ぎる文官達の中にヘイツを見付け、ラインハルトはヘイツに話しかけました。二人の話を聞いていたビルヘルムは、ヘイツを見つめたまま「この人は誰ですか?」と尋ねます。ラインハルトはヘイツを紹介し、サラ婦人を助けるために財務庁から人を連れていくことになったと説明しました。
ヘイツと別れた後、ビルヘルムはラインハルトを送り届けたら皇室騎士団をまとめるイーロン卿に呼ばれているので出かけることを報告しました。
ラインハルトを送り届けたビルヘルムは出かけたが、それはイーロン卿に会うためではありません。皇帝から出自を証明するためにもらった皇族の証であるアマリリス牌を見せ、倉庫に入りました。見せられた護衛騎士たちは私生児の存在について知らなかったけれど、その牌を見て「皇帝か皇太子の命令で動いているのだろう」と勘違いし、ビルヘルムに従いました。
そうして倉庫の中を漁り、ビルヘルムはようやく目当てのものを見つけました。ラインハルトの少女時代の肖像画でした。
その肖像画を鑑賞し、膝をついて絵の彼女の頬に口付け、彼女の首筋や鎖骨を撫でた。それは布地に書かれた絵だったが、それでもビルヘルムはうっとりしました。ビルヘルムは元々ここにこの肖像画があることを知っていたけど、アマリリス牌を貰えなければ今日見に来ることは出来なかった。
ビルヘルムはラインハルトの肖像画を見つめながら、柔らかい彼女の手が自分の首を締めるところを想像し、実際に首を絞めてみました。息苦しくなってすぐに手を離し、肖像画をまた布で丁寧に巻いて倉庫の奥にしまいます。さすがに今すぐ持ち帰ることは出来ないのは理解していました。
ビルヘルムは倉庫を出たあと、ヘイツについて考えました。ビルヘルムの知らないラインハルトの人生の軌跡の一つなのだろうと思いました。しかし気に食わないしので、いっそ城ごと燃やしてしまおうかと考えます。
全て燃やしてラインハルトだけ攫い、首輪をつけて眼帯をつける。黄金の瞳が涙で溢れようが、一生自分さえ見てくれるなら耐えられる。そんなことを考えていると「おい、こら」という自分を叱り付ける声が聞こえました。ディートリッヒは過去に「それは愛じゃない」と言ってビルヘルムを叱りつけ、「お前も年をとったらわかる」と言った。けれど、ビルヘルムは本当ならディートリッヒより長い歳月を経験してきたのに、歳月を過ごすだけでは分かりませんでした。
ビルヘルムも回帰していたことがここでようやく明かされましたね。
ブドウ
アルゼンはアマリリス牌を見せられ、ビルヘルムが皇帝の私生児だという事実を確認し、ペルナハが首都に向かっているという報告をラインハルトにしました。ビルヘルムが私生児と確定した以上、グレンシアを筆頭にミシェルに挑む事になりますが、その最大の敵がカストレヤ皇后でした。今の皇帝をその地位に押し上げたという功績もある上に、皇帝とはいとこ同士だったので、血筋からいったらミシェルが有利です。
3週間後に行われる大宗教会で、恐らく火蓋が切られます。ラインハルト達も長期戦を望んでいなかったし、皇帝もミシェルに宣戦布告するのを望んでいたから。
ビルヘルムは食事が進まないラインハルトのために、ブドウの種を取ってから皿を差し出しました。ビルヘルムにどう思っているのかラインハルトが聞くと、ミシェルの首を切ると人々が喜ばれるから光栄だとビルヘルムは答えました。
「その首をあなたに捧げたらどうですか、ラインハルト」
ビルヘルムはブドウを一つ掴んでラインハルトの方に差し出しました。ラインハルトが口を開けるとブドウをラインハルトの口に入れ、さりげなくラインハルトの舌と唇を触った。ブドウを飲み込んだラインハルトはビルヘルムを呼び、「ミシェルの首に刃を突き刺すのは私でなければならない」と言いました。
「それはあなたにも譲れない。わかった?」
「……俺の主人は本当に気難しい」
ラインハルトはビルヘルムについて考えました。ラインハルトはこれまでミシェルの首を切り、その血を飲む事だけを考えてきた。しかし、ビルヘルムが介入した事によってラインハルトは裕福になり、遠かったその首まで手が届きそうになっています。
ラインハルトは父の言葉を思い出しました。
『わからない時ほど自分を見なさい。他人ではなく、お前が望むものが何なのか、望まないものが何なのかを考えなさい』
ラインハルトの望むものは分からなかったけど、ラインハルトが裕福になった理由はビルヘルムにあった。これまでビルヘルムにぎこちなかったのは、彼がラインハルトに求愛して来たからという理由だけではありませんでした。
2巻前編を読んだ感想
2巻の7章ながーーーーーーーい!そして今回ビルヘルムの回帰も明かされたので、少し物語が複雑になってきましたね。そして、不穏なビルヘルムとドルネシア…
吐き気を催すということなのでビルヘルムには企みがあるのでしょうが、読んでいて嫌な気持ちになりました。お前の尻尾はラインハルトにだけ振ってろ!フリだけでも他に振るんじゃない!と思いました。
2巻の記事は前・中・後で3記事に分かれる予定です。次回の更新はtwitterにてお知らせします!
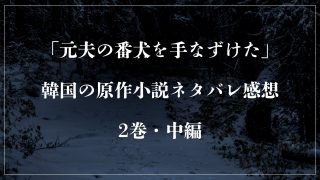

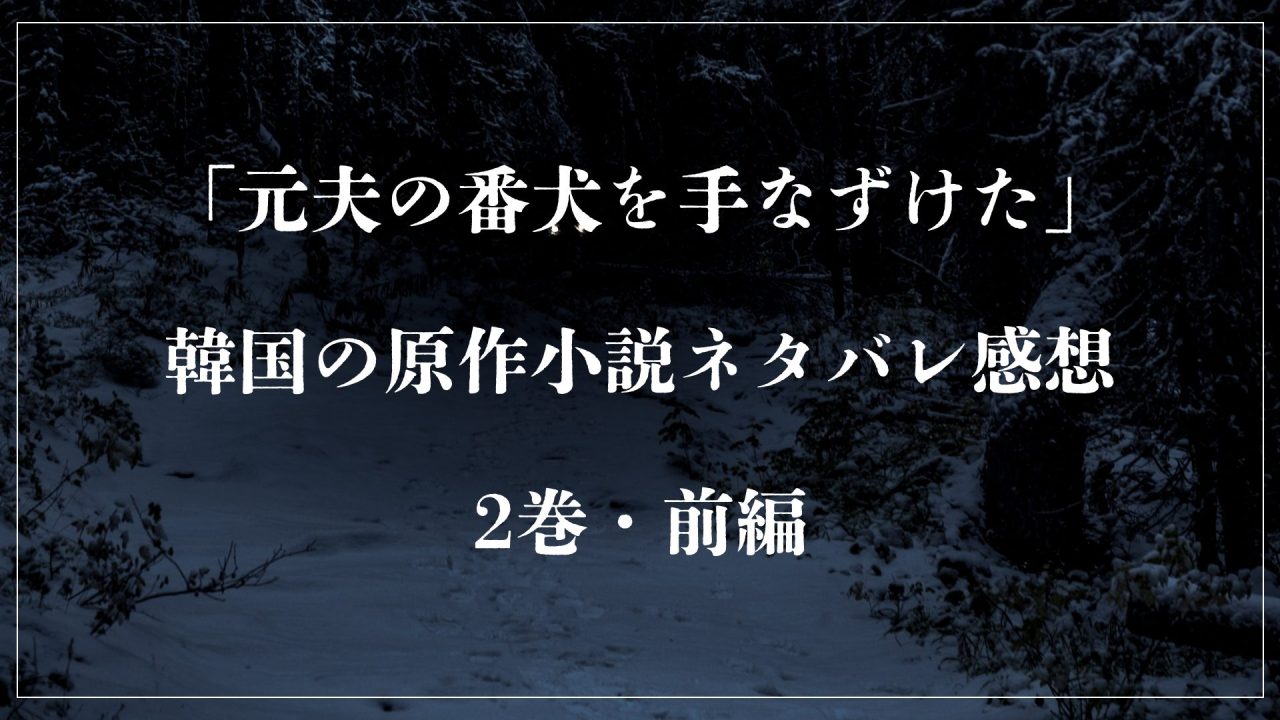
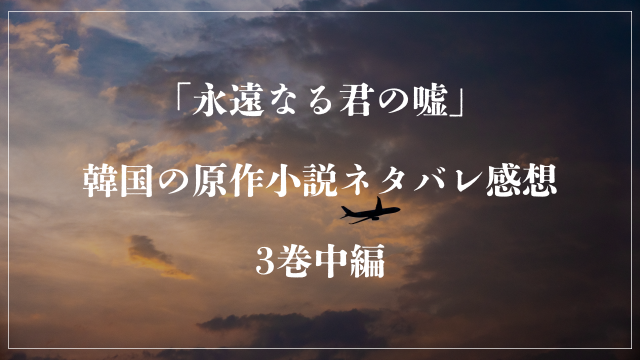
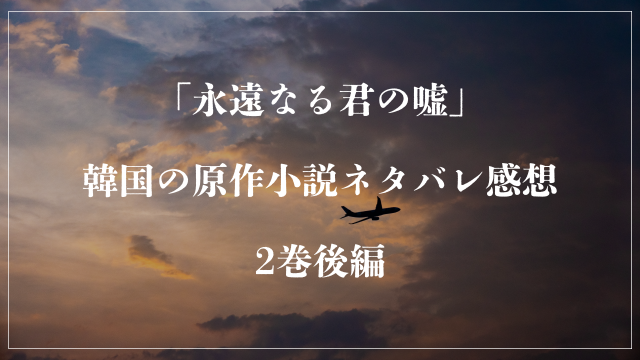
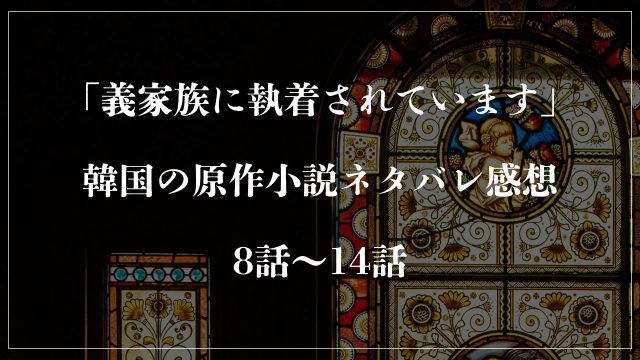
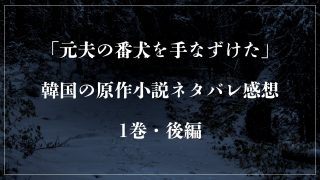

なかなか原作のネタバレ感想記事がなかったので助かります!
ディートリッヒの行方が気になって仕方ないです。笑
そしてあのクソ女、、漫画だと無駄に美しいので悔しいです。笑
みみさんコメントありがとうございます!
漫画だとどのキャラクターも美麗なので、目の保養でもあり、同時に悔しくもあり…
ドルネシア。性格を知らなければ美人ですもんね。わかります…