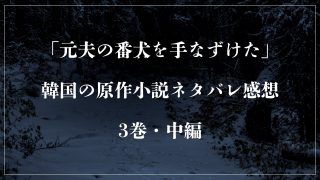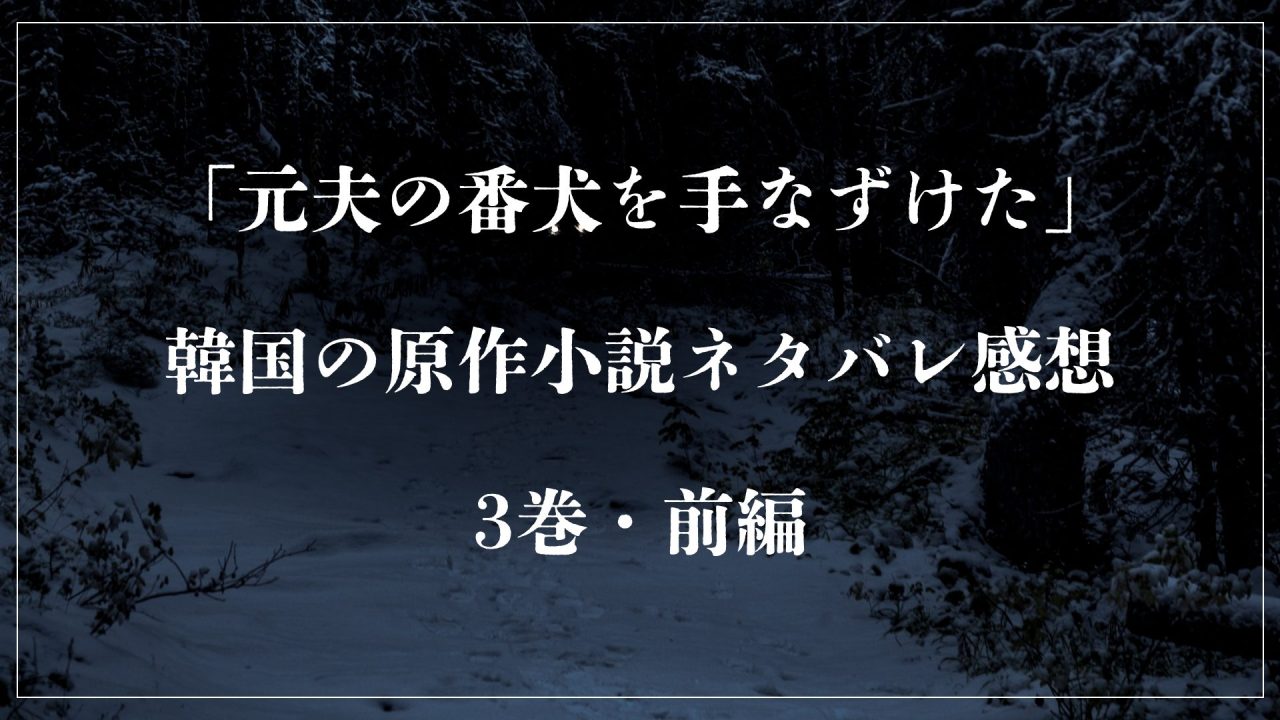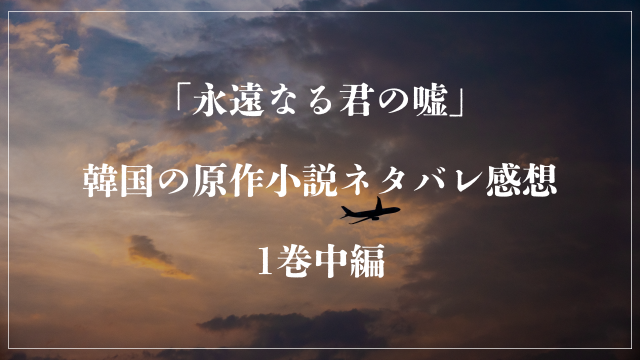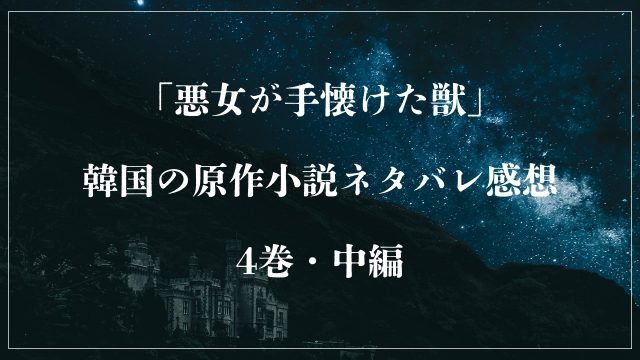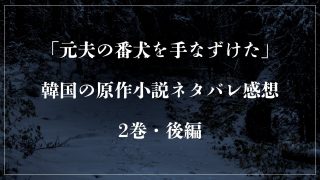コミカライズ連載している「元夫の番犬を手なずけた」の韓国原作小説を読んだのでネタバレ感想を書いていきます。韓国語は不慣れなので翻訳が間違っていることもあります。
(間違っているところを見つけた場合はtwitterのDMでコッソリ教えてください…)
元夫の番犬を手なずけた(전남편의 미친개를 길들였다)
原作:Jkyum

11.犬の話
ビルが物心つく頃には一人だった。寒い北部で、時折ビルは人に拾われたが、「狂った奴!」と言われて追い出される。たまに親切な人もいて、ビルをこき使う代わりにパンひとつを与えてくれました。ビルは、それが親切だと思っていました。
春になりかけた季節、北部にやってきた皇太子夫妻の乗った馬車は雪解けの後は道が泥でぬかるむのを知らなかったのか、馬車の車輪が泥に沈んでしまっていました。
それを、当時すでに人より体の大きかったビルが助け、ドルネシアがミシェルから渡された金貨をビルに与えようとした時、ビルの腹の音が鳴りました。
「可哀想に、食事もできなかったようですね」
そう話すドルネシアの安い同情に乗らなければ良かったと、ビルは後になって後悔します。
ビルは小銭を何枚か貰えれば十分だったけど、この後の道も同じような状態なので次の目的地まで連れていこうとドルネシアはミシェルに頼みました。ビルはドルネシアの生ぬるい視線が嫌で断ったものの、白いパンと乾燥肉に釣られて結局次の都市までついて行くことになりました。
しかし、北部では当たり前の「悪魔の夜」のことをミシェル達は知らなかった。初代皇帝アマリリスによって、酷い寒さになる夜は白いアマリリスの花が咲きます。数年に一度しか訪れないけど、そうした夜は寒さで凍え死ぬか、魔物に殺されるかなので、北部の人間は悪魔の夜に外出はしません。
悪魔の夜、ビルの静止は聞きいれて貰えず、結局夜の道を進んだ皇帝夫妻は魔物に襲われました。騎士たちは魔物によって殺され、馬車を襲われているところをビルが助けると、ミシェルは首都にビルを連れて帰ることにしました。ビルはミシェルの護衛騎士になり、水晶門をくぐった時、ミシェル達はビルの出自を知りました。
皇后は激昂してすぐに殺せとミシェルに言ったけれど、ミシェルはビルを殺しませんでした。ビルは騎士団に徐々に慣れ、やがてそこで一番強くなりました。
「ああ、ビル。今日も素敵ですね」
ドルネシアはビルを他の騎士より大切にしていたけれど、それは居場所のなかったドルネシアが自ら居場所を与えたからでした。周りはそんなドルネシアとビルの関係を怪しみ、怒ったミシェルによってビルは戦場に捨てられたけど二ヶ月後に生還しました。さらに戦場に送られても、ビルはいつも帰ってきました。
やがて人々はミシェルが優秀な騎士を連れてきたのだと彼を褒めたたえるようになりましたが、ビルは以前の生活の方が良かった。
ミシェルは最初にビルを戦場に捨てた時、ドルネシアにも怒り、「可哀想だったから」というドルネシアに「お前こそ、この皇室で一番可哀想な女じゃないか」と言い捨てました。ドルネシアがビルを気にするのは同情心ではありませんでした。自分より低い位置にいるビルを見て自分を慰めていました。
ビルはミシェルに「どうしてお前なんかが!」と訳も分からず殴られました。ミシェルは自分よりも大きなビルに劣等感を感じていたし、綺麗にさらけだしているその顔が自分と似ている、もしくは自分以上に整っていることに、腹を立てていました。
「お前はどうして殴られているのかわからないだろう。下賎だからだ」
ミシェルはそばにいたドルネシアに「手が痛いからお前がかわりに打て」と鞭を渡して命じ、逆らえないドルネシアによる鞭打ちが始まりました。
最初は怯えていたドルネシアが段々と顔つきが変わるのを見て、ミシェルは自分が支配していると思って喜びました。けれど、ドルネシアはむしろ自分よりも大きな男が自分に殴られても仕方ないという光景に喜びを感じていました。いつも怯えていたドルネシアにとって、暴力は砂糖のように甘かった。それからドルネシアは様々な言いがかりをつけて度々ビルを頬を殴るようになりました。
ミシェルはビルに髭を伸ばして顔を隠すようビルに命じました。それだけビルの綺麗な顔に対して劣等感を持っていたのですね。
暴力が終わるといつもドルネシアは優しく声をかけますが、ドルネシアはビルにうつ伏せになれと命じたりもしました。鞭が振るわれる時もあれば、口付けがやってくることもあった。
そうして首輪を付けられたビルは、ドルネシアに「ドルネシアと呼んでください」と言われ、そのまま名前を口にしたら頬を殴られ、首を絞められました。
「ごめんなさい。私は誰かがむやみに私の名前を呼ぶのが死ぬほど嫌なの。でもあなたは好き。私の前で跪くあなたを愛してる。あなたもそうでしょう?」
そこまで聞いて、ラインハルトは耐えられずにビルヘルムの話を遮りました。ラインハルトはドルネシアのことをこれまで気にしてこなかった。しかし、ミシェルにしてもドルネシアにしても、あまりにも簡単に死んだのではないか、と思えてきました。
そしてラインハルトは自分がドルネシアと変わらないのではないかと思い始めますが、ビルヘルムは「大事なのはここからの話です」とラインハルトの指に口付けをしました。
「首輪をはめられた犬が、どうして他人を主人として崇拝するようになったのか不思議ではありませんか?」
それは自分がそのように育てたから。そう言うとしたけど、ビルヘルムの指によって塞がれました。
指はラインハルトの傷ついた左鎖骨をまっすぐ横切った後、首筋に沿って左頬まで上がった。真っ赤で恐ろしい傷の上を恍惚と眺めていたビルヘルムは、ふと彼女の目と視線を合わせた。
夢で見たような、星も飲み込んでしまいそうな真っ黒な瞳。
「いいえ、ラインハルト。 俺はあなたのことをずいぶん前から知っていました」
「………」
「あなたが俺を知る前からです」
ドルネシアはビルが戦場から帰る度に加虐的になっていきました。ミシェルにもその話が届いたけど、ビルが従順なので問題ないとミシェルは判断しました。
「犬が言うことを聞かないのなら罰を受けるのは当然だ。ましてや道具を犬扱いしてやってるんだ。感謝して欲しいくらいだ」
戦場だけがビルが解放かれる場所でした。ビルは自分の中に怒りと残虐さを持っていたけど、それらは戦場で使われました。水晶門を通る度に必要のない水晶がビルの元に溜まったけど、ミシェルは同じ血が流れているのを認めたくないのか、水晶を返されることさえ嫌がりました。
皇帝となったミシェルは、本来は皇帝の親友に与えるべき特別な爵位である「七つの聖地の主」をビルに与えました。皇帝に直接意見を言える権利を持つ爵位であり、必ず一人は居なければいけない決まりがありました。つまり、皇帝が最低一人の意見を聞くように、というものでしたが、それを調教したビルに与えました。
ビルはアマリリス牌も与えられ、好きな場所に行くことが出来たけど、調教された犬は他に行くところがわからず、皇太子妃宮をさまよいました。皇后となったドルネシアはすでに宮を移していたが、それをビルは知らなかった。そうして、ビルは一つの倉庫に入り、そこでは少女の肖像画を見つけました。
最初はそれが誰なのかも知らなかった。布に隠された頬がリンゴのように赤く、皇室の画家が描いた金髪が日差しにきらめくのが不思議と目に入った。
青年は思わず肖像画の上に覆われた布をはがした。布の中に隠されたのは少女だった。皇太子妃に決まったばかりの興奮気味の、そして画家の前でポーズをとるのが照れくさくて顔を赤らめた10代後半の女の子。金色の目は日光を浴びて美しく輝き、まっすぐな額と目元には生き生きとしていた。
そして、その下に書かれた名前を見て、ビルはようやくそれが誰なのか分かった。
ミシェルはラインハルトについて時折酒の席で「つまらない女」だと言った。しかし、ビルの目に入ったラインハルトの姿は全く違っていました。その輝く瞳と、誰もが恋に落ちるのでは無いかと思うほど暖かな顔。青白い肌の下で紫色の血が流れていそうなミシェルとドルネシアばかり見てきたビルにとって、とても衝撃的でした。
慌てて倉庫を飛び出したけど、その夜は一晩中少女の顔が頭から離れられなくて、結局ビルは次の日また倉庫を訪れました。
ビルはミシェル達にラインハルトついて尋ねましたが、ミシェルは尖ったものを使ってビルを殴り、ビルの右眉には大きな傷ができました。
それから、ビルは皇城に行くと倉庫に立ち寄る日々が続きました。笑顔を浮かべる肖像画を見て、今まで一度も自分は笑顔を向けられたことがなかったけど、まさにこの絵の少女と出会うためなのだとビルは思いました。
そうして限りなく肖像画を眺める日々が続いた、とある日。ビルは衝動的に肖像画に口付けをしました。
肖像画からは古い絵の具とほこりの匂いがしたけど、ビルはそこで自分が恋に落ちたのを自覚しました。ラインハルトの近況を調べるのは簡単で、彼女はヘルカの領主になっていたので、どうやったらヘルカに行けるのかと、ビルは地図を見て過ごす日々が多くなりました。
ビルの副官のエゴンはビルが地図を見るのは戦争を起こすためだと思ったようでしたが、ビルの目的は違いました。周辺を巡察する目的だとしても、ヘルカは距離がある。そこで、帝国が頭を悩ませている南部の土地があることを思い出し、ビルは初めてミシェルに自分から出征を申し出ました。
ヘルカに立ち寄るために南部での戦いに勝ち、そのあとにヘルカにわざわざ立ち寄った。しかし、現れたのは生き生きとした愛らしい少女ではなく、痩せて目がくぼんだ年配の女性だった。
声はかすれ、顔は青ざめているラインハルトを見て、誰が彼女のリンゴのように赤かった顔を奪ったのだろうかと考えたけど、答えは分かりきっていました。
ラインハルトはビルと短い言葉を交わしながら食事を口に運びましたが、それも振りだけで、彼女が食べたのは豆二粒とあとは酒だけ。
「シュバリエの誓いもしていないのに、皇帝はなぜあなたを10年も戦地に送るのでしょうか」
道具を正しい場所で使うだけだとビルが答えると、ラインハルトは酒の匂いを漂わせながら「本当にそう思いますか?」と尋ねます。
「元皇太子妃という道具についてはどう思いますか?」
先程まではくぼんで見えたラインハルトの目には生気が宿っていました。雪の中で燃え上がるような憎悪。ビルヘルムはこれほど輝いている憎悪を見たことがなかった。
「人は道具ではありません。それをあいつは知らない」
その怒りの言葉を聞いて、ビルは再び恋に落ちた。今度は絵ではなく生きているラインハルトに。
ビルはそのあと三日間ヘルカに滞在し、ずっとラインハルトについて考えました。結局落ち着かなかったビルは最終日の夜に城を歩き、中庭で言い争うヘイツとラインハルトの声を聞いて足を止めます。
「いくら仇を撃つと言っても、本人が健康でなければ復讐もできませんよ。領主様の体調なら生まれ変わった方が早そうですが」
「生まれ変わることが出来れば、あいつを絶対に殺してやる」
話を聞いていたビルは自分がミシェルやドルネシアに剣を突きつけるところを初めて想像し、あの銀髪が血に染まると思うと不思議な気持ちが沸き立ちました。
首都に帰ったビルは肖像画のラインハルトを眺め、この少女がどうして憎悪に満ちた目つきになったのか気になりました。それは、何かを気にすることのなかったビルにとって驚くべきことだった。
その夜、ビルは夢にラインハルトが現れ、その手に首を絞められて目を覚ました。ビルはラインハルトに自分を所有して欲しかった。ビルの首輪を持つのがドルネシアではなくラインハルトであることを望みました。ベッドから流れる髪が、銀髪ではなく金髪であることを望んでいました。
ビルヘルムの眉にある傷がミシェルによってできた傷であり、前回の人生ではミシェルとドルネシアに散々な目に遭わされていたのが明かされました。
ビルはラインハルトが欲しくて、ついミシェルの前で「欲しいものがあった時はどうすればいいですか」と聞いてしまい、ミシェルは自分の王座を欲しがっていると勘違いしました。ミシェルはすでにドルネシアが自分を裏切っていることは知っていたけど、王座まで欲しがるのなら処分すべきだと考えました。
ビルはミシェルによって魔物や野蛮族がいる北部の国境線に出征し、そこで一緒に出征していた騎士に裏切られ、ビルは冷たい大地に倒れました。ビルがいつも胸にしまっていた水晶が騎士によって回収され、その際にアマリリス牌が雪の上に落ちた。日光が反射し、その光を受けながらビルは「もう一度あなたに会いたい」と願いました。
ラインハルトが南部のヘルカで息を引き取った日、偶然にもビルも同じようにその生涯を閉じました。
そうしてビルが二回目の人生に戻ってきた時、自分自身も自分が戻ってきたということを理解していませんでした。前世と違っていたのは眉の上の傷ですが、その自覚もないまま森をさまよい、そこで女性の悲鳴を聞き、木の実を投げて助けました。
「ビルヘルム。そうだね、ビルヘルムがいい」
ビルではなくビルヘルム。それが少年の名前だった。女はそうして、ビルヘルムの世界になった。
無自覚のままビルヘルムは少年時代を過ごし、ラインハルトが自分に向けてくれる暖かな目を見るのが好きでしたが、それはディートリッヒが現れたことによって壊されます。
ラインハルトはビルヘルムを抱きしめてくれるけど、ディートリッヒにはしない。そのことに密かな満足感を得ていましたが、ラインハルトは時折ディートリッヒの肩にもたれかかって彼を頼りにしていました。
ラインハルトがディートリッヒに時折向ける複雑な感情が混じった目も、ビルヘルムがディートリッヒを警戒する理由の一つで、ラインハルトの初恋相手だと知ってからはその警戒はさらに強くなりました。
戦場でもディートリッヒと親しくなるつもりは無かったので、むしろ別の場所で良かったと思うくらいでした。
ビルヘルムは戦場で認められていたけど、誰も親しくなろうとしなかったので、ビルヘルムは常に戦場では一人だった。そしてその油断している隙にリンケ侯爵の剣が野蛮族の大族長の息子に奪われ、ラインハルトの布がそいつの血まみれの指で汚れた時。ビルヘルムは激しい怒りと共に、強烈な痛みがこめかみを襲いました。
『犬が言うことを聞かないのなら罰を受けるのは当然ではないか?』
何も聞こえなくなり、ビルヘルムは目の前に迫った大族長の息子を殺して剣を取り戻しました。ビルヘルムはそこから一ヶ月頭痛に苦しみましたが、殺戮をすれば徐々に痛みは引いていきました。そうしてビルヘルムは、ビル・コルーナの記憶を思い出した。
そして、かつてのラインハルトが生まれ変わって確かにミシェルに怪我を負わせたのだと知って、今すぐにラインハルトに会いに行きたくなるほどでした。それを止めたのはディートリッヒで、ディートリッヒは「子爵様に安否の手紙は書かないのか?」と尋ねます。
何を書けばいいか迷ったビルヘルムは、ラインハルトのことを考え、彼女が欲しがっているものを考えました。それはミシェルの首だった。
「その時から俺は戦争に没頭するようになりました」
「いつも俺に笑ってくれるあなたが好きでした。俺に人生を教えてくれた人だから当然だと思いましたが、あなたを見る度に心の片隅に隠された罪意識が俺を苦しめました。当然のことです。欲しがってはいけない人を欲しがったので」
背筋が冷たかった。遥かな意識の向こうから欲張った女性が今、自分の胸に抱かれていた。ビルヘルムは高見が目前に迫っていることを直感した。遠く感じられた過去の歳月が忘れられる瞬間だった。
過去の記憶を頼りに族長を探し出し、一人一人ビルヘルムは殺しました。しかし、そうして最後にはディートリッヒの命が散ってしまった。ビルヘルムはラインハルトに謝りました。ラインハルトはベッドの上で身を起こし、ビルヘルムの首を抱きしめました。
「正直恨めしい気持ちもあるけど、でもディートリッヒはあなたにとってもそれだけ強い人だったのでしょう。死ぬなんて思いもよらないほど。私はあなたを恨まない。愛しているわ」
「……ラインハルト」
喜びに満ちたビルヘルムはラインハルトを抱きしめました。
「私が欲しいの?」
「はい、いいえ、はい、いや…」
興奮のあまりしどろもどろになったビルヘルムは、しばらく躊躇ったあと「俺の主人になって欲しいです」と言いました。
ビルヘルムはラインハルトの手を自分の首に持っていき「俺を生かすも殺すのもあなたの役目ですから」と耳を赤くさせながら言いました。ビルヘルムの望みを知ったラインハルトはそのままビルヘルムの首を握りしめます。
「いつもあなたに振り回されたいです」
「……怖い」
「怖がらないで。俺の死も人生も完全にあなたのものであることを疑わせないでください」
ラインハルトは自分を見つめるその目を見ながら、ゆっくり力を入れた。
「ライン、ハルト……」
「…………」
「俺は、あなたのもので……」
話していたビルヘルムが呻き声をあげたので、ラインハルトは慌てて手を離しました。しかし、興奮したビルヘルムがラインハルトの腰を抱きしめ「大好きです」と言います。
「俺の主人。愛しています。本当に愛してる」
ラインハルトの肌に顔を埋めたビルヘルムは、まるで祈るかのようにつぶやいた。 神を崇拝する狂信者がこうなのだろうか。
「あなたが俺に死ねと言っても、俺は喜んで死にます、ラインハルト」
ラインハルトは口を閉じてビルヘルムの耳を撫でた。興奮と喜びに染まった顔で夢中になって騒ぐ青年の言葉が、彼女まで熱くさせた。
かつて、不安だったラインハルトは自分がビルヘルムのおもちゃなのではないかと考えたことがある。その不安を知っていたビルヘルムは、ラインハルトの胸のリボンをほどき、自分の首に巻き付けて、リボンの先をラインハルトに握らせました。
「俺の方があなたのおもちゃになれなくてヤキモキしていたのに」
ラインハルトは笑いながらリボンを引いてビルヘルムに顔を寄せました。
12.幸福の絶頂
皇太子妃が死に、その時監獄を守っていた警備兵達も死体となって発見されました。皇后はベッドが起き上がり、自分の手で殺せなかった事を悔しがったけど、誰もが皇后が皇太子妃を殺したのだと思いました。
皇太子殺しが確定していたため、ドルネシアの遺体は焼かれ、その遺灰は皇城の下水道に捨てられました。
皇后は青白い顔で会議に向かっていました。皇太子が亡くなったため、順当に行くなら次の皇太子はビルヘルムですが、怪しい噂もあるので大貴族たちで話し合う事になっていました。
皇后が入ると会議場は既に賑わっていて、誰もがラインハルトを褒めていました。今まではどんなに賑やかでも皇后が入るなり静かになるはずなのに、今では彼らは最小限の礼だけして、また会話に戻ってしまった。
その中心にいるのはラインハルト。いつもは喪服を身につけ、化粧けのない地味な出で立ちでしたが、今日は違っていました。
金の髪は繊細に編み上げられ、星の形をした金の装飾が髪に埋め込まれていました。一見すると髪の毛ではなく黄金の棺のようで、またラインハルトが身につけているのも目が覚めるような真っ赤なドレスでした。首から頬に繋がる金の装飾は、まるで繊細な花のようにその下にある肌を隠していました。
ラインハルトは皇后を見るとにこやかに笑って一番簡単な礼をしました。その瞬間、皇后はまるで舞台の幕が落ちて終焉を迎えたかのような気分になり、力が抜けて崩れ落ちた。貴族たちは驚くふりをしたけど、自分の侍女以外、誰も皇后に駆け寄らず、皇后は気絶しました。
その日、貴族たちの多数決によってビルヘルムが皇太子になることが決定しました。
赤い邸宅の前には皇太子となったビルヘルムと、彼を拾って皇太子にまでしたラインハルトを見ようと人々が押し寄せました。
貴族たちは宴会を開いて二人を招待し、二人はどの宴会にも現れました。ラインハルトは毎回違うドレスで現れ、ビルヘルムはそんな彼女のそばに影のように付き従っていた。
先日はミューラー伯爵家の宴会で、ラインハルトは友人である婦人のために首都では誰も見た事がない規模の花火を打ち上げました。
ラインハルトの本音は、この花火はミシェルの死を華やかに祝うためでしたが、誰もそんなことを知らなかった。
ビルヘルムは皇太子宮で過ごすのではなく、赤い邸宅でラインハルトと一緒に過ごしました。マルクはその時間を邪魔したくなかったけど、それでも先延ばしに出来ずにラインハルトの元を訪れました。いつの間にか寝室にはビルヘルムによっていくつかの衝立が置かれていました。
「今日帰るの?」
「はい」
マルクがルーデンに帰る日でした。元々マルクは兵士でしたが、首都で気を許すことができなかったラインハルトのために侍女になって残っていました。すでにミシェルは死に、皇后はうつ病となって皇后宮から出られなくなり、危険は去りました。
おまけにビルヘルムがラインハルトを守っているのは周知の事実なので、ラインハルトの元には手先の器用な侍女が新しく来ていました。
「結婚式に出れないのが残念ね」
「あはは、結婚式に主人が出るなんて」
マルクにはルーデンで同じようにラインハルトに仕える侍従の婚約者がいました。ラインハルトは首都に長居させてしまったせいで結婚が延期になったことをマルクに謝りました。
「何を言ってるんですか。領主様のおかげで私がどれだけ楽になったことか。だって私の母は小さなルーデンスの使用人じゃなくて、今や大領地の全権代理人です」
延期になったおかげで地位があがり、全権代理人のサラ婦人の娘であるマルクの結婚式では、ワイン20本と城の中庭を使っても良いという許可が出て、ラインハルトはマルクに金のネックレスと貴重な白狐の毛皮を贈りました。
そこへ、衝立の奥から気だるげにビルヘルムが出てきました。ベッドを今抜け出してきたかのような姿にラインハルトは笑いながらビルヘルムは窘めましたが、ビルヘルムは自分が贈り物を送っても受け取らないのになぜマルクにはむしろ与えているのかと不満を言いました。
ビルヘルムから贈られるプレゼントが赤い邸宅とその他3つの倉庫がいっぱいになったので、ラインハルトはそれ以上は受け取れなくなり、貰ったものは全て皇城の倉庫に返していました。
ラインハルトはマルクがルーデンではなくしばらくオリエントにいることになると聞き、「それならオリエントに戻ったらまた毎日会えるから寂しくないね」と言いました。それを不満に思ったビルヘルムがラインハルトの名前を呼び、ソファに座るラインハルトを後ろから抱きしめます。
当初、ビルヘルムは皇太子になるのを拒否しましたが、ラインハルトがしばらく赤い邸宅に残ることを条件で受け入れました。しかし今後について二人の意見は合っていないようだとマルクは思いました。
「俺はあなたの言うことを聞いたのだから、あなたも首都の大貴族として生きてください」
「放ったらかしにすることはできないし、私はまだ自分の領地を一度も見て回ったことは無いのに」
ビルヘルムは顔を顰めてラインハルトの耳を噛みました。
「犬は飼い主を噛むかもしれません」
「ビルヘルム!」
「やっぱり俺たち結婚しましょう。ね?」
「あなたと結婚したら私はルーデンを皇帝の口の中に入れなきゃいけなくなる」
ラインハルトはビルヘルムに「この話を持ち出したら心を傷つけることしかできないを知ってるでしょ」と言って叱ると、ビルヘルムは黙ってラインハルトの隣に座り、ラインハルトの腰に抱きつき、肩に顔を埋めました。
ラインハルトはマルクが結婚式をルーデンで挙げることを聞き、そのついでにディートリッヒの墓を見てきて欲しいと頼みます。ラインハルトはディートリッヒを思い出して「戦争というのは本当に…」と言いました。
「いい人ほど天が早く連れて行ってしまいますね」
「そうね。でもそんないい人が何も残さず去るなんて」
マルクは、思わずラインハルトに駆け寄って手を握りたかった。
「遺体もなく剣もないなんて」
最後の戦闘は確かに壮絶な死闘戦となった。多くの兵士の遺体が見つからなかった。けれど。
「でも、あの」
マルクが言葉を続けようとしたけど、ラインハルトの腰を抱いていたビルヘルムの目がマルクに向いた。その獰猛な獣のような目は、マルクに「黙れ」と言っていました。
「どうしたの?マルク?」
するとビルヘルムは表情を一変させ、「マルクが寒そうです」とラインハルトに言いました。ビルヘルムは自分が贈ってラインハルトが受け取らなかった物の中からマルクに贈り物をすると話し始めます。
マルクは断ろうとしたけれど、マルクを眺めるビルヘルムの目つきは高圧的で、贈り物というより脅迫をしているようでした。
「どうか受け取って、末永く元気で」
ここでディートリッヒに関して不穏な雰囲気が出てきましたね。
宴会続きで酒の量が増えたラインハルトは夜に暑さで目が覚めました。自分に巻き付くビルヘルムの腕を引き剥がして水を飲み、復讐を終えた今後の人生について考えます。
そしてふとビルヘルムに与えたリンケ侯爵の剣が目に入り、ラインハルトはそれを手に取ると、刃が真っ黒に変わっているのを見つけました。
管理のせいかと思ったけど、ラインハルトがあげたものをビルヘルムがそんなことをするはずがありません。ベッドに腰掛けて、眠っていたビルヘルムに尋ねると、やや時間をあけてから「俺にも分かりません。最近急に変わりました」と答えました。
起き上がろうとするビルヘルムを「私も寝るからもっと眠って」と言ってベッドに戻しながら、ラインハルトは「剣が役目を全うしたからそうなったのでは」と口にしました。
「何の役目ですか?」
「全部終わったから」
ビルヘルムは現在皇太子のための教育を受けている最中で、その日程は殺人的に忙しかった。ラインハルトがビルヘルムの頭を撫でているとやがて眠り、ラインハルトは笑いながらそばにあった剣を観て、そこに巻かれた布を何度捨てさせようとしても言うことを聞かなかったことを思い出します。
しかし、さすがに皇太子が持つべきものでは無いので、少し整えてあげようと思ってラインハルトは布を剣から取ってから解いきました。しわくちゃな布は不思議と記憶より長いと思った時、急に寒気を感じました。
「何してるんですか」
耳のすぐそばで聞こえた低い声に驚いて剣を落とし、ビルヘルムは無表情のままラインハルトを覗き込みました。
「布が古すぎるから少し整えようと思って。起きたの?」
ビルヘルムはそれには答えずに剣を奪い、鋭い目をしながら布をまた取っ手に巻き付けた。
「必要ありません」
「でも……」
「大丈夫です、ラインハルト」
ビルヘルムは剣をベッドの下に置き、ようやくラインハルトと目を合わせたけど、ラインハルトは何だかすっきりしない心地を味わいました。
ビルヘルムは「このままでいいですよ、俺は」と言って、ラインハルトをベッドに引きずり込みました。思えば少年の頃からラインハルトが理解できないものに執着をする子だったとラインハルトは考えました。ビルヘルムがラインハルトの首筋に口付けたので、ラインハルトはそれ以上考えることはできなくなりました。
リンケ侯爵の剣に巻きつけた布に関しては、時折怒ったような態度をしていますね。該当箇所はこちら。
新年の宴会では皇帝は早々に退席し、皇后は出席していなかったので、自然と主役はビルヘルムとラインハルトになった。
しかし、ラインハルトが何人かの貴族に挨拶を受けているのを見て、さすがに我慢できなくなったビルヘルムはラインハルトをテラスに連れ出しました。
ビルヘルムはラインハルトの手の甲に誰かが口付けるのも、ラインハルトが誰かと踊るのも気に食わなかった。
「そのうち侍女にまで嫉妬しそうだね」
答えなかったビルヘルムを見て、ラインハルトは笑いました。
「今は虎視眈々とあなたにプロポーズしようとしているやつらの目玉を全部抜いてしまいたいのを我慢してるんです」
ラインハルトはテラスにこしかけてビルヘルムの胸に額を押し付けながら「私は誰とも結婚しないよ」と言いました。
「でも今はあなたを愛してる。知ってるでしょ?」
「ラインハルト、あなたはまだ俺がいつかあなたを手放すと思っているんですか?」
ラインハルトが膝に視線を落とし、そこにある傷を思い出していると、「俺を信じていませんよね?」とビルヘルムが言います。
「みんなを信じてないだけ」
「だから俺も信じないという事ですね」
ミシェルを毒なんかで殺してしまったことを今更ながらビルヘルムは後悔しました。
「俺は今毎日が幸せです。前世では目を覚ましたくない日もありました。大きなベッドも怖かった。けれど、ラインハルト。あなたとベッドにいると幸せなんです」
でも時々不安になる、とビルヘルムは続けます。前にラインハルトが、ビルヘルムをベッドに引入れるのは平気だと取引を持ちかけた時に言ったから、いつかラインハルトはビルヘルムを捨てて去ってしまうのでは無いか、と言いました。
「俺を信じないあなたが、俺だけを信じさせるようにするにはどうすればいいですか?もう俺があなたに差し出せるものはないのに」
復讐は既に終わってしまったから。しかしその復讐をラインハルトに与えたビルヘルムこそ、ラインハルトは信用しなければならなかった。
しかし、どうしてか口が重たかった。前世まで渡って完璧な贈り物をしてくれたビルヘルムを愛することはできても、信じることがなぜかラインハルトにはできなかった。それは、結婚の誓いをしたミシェルがあまりにも簡単にラインハルトを捨てたからなのだろうか、とラインハルトは考えました。こんなに幸せなのに、二人とも不安だった。
「ビルヘルム、あなたほど完璧な贈り物をくれた人がどこにいるの。……あなただけは信じてるよ、ビルヘルム」
ラインハルトは自分に言い聞かせながらビルヘルムに言いました。ラインハルトがビルヘルムを信じられないのは今まで歩いてきた道が険しかったからで、幸せなのに不安なのは、ラインハルトが幸せを甘受した事がないからだと思いました。
「俺にはあなただけです。あなたさえいれば他はどうでもいい。だから今あなたがそう言ってくれるのが嬉しいです」
ビルヘルムは跪いてラインハルトの膝に額を乗せました。ラインハルトはビルヘルムの頭を撫でながら、水晶門があるのだからいつでも会える、と話しました。それでもついて行きたいというビルヘルムに、ラインハルトは「復讐が終わっても人生は続くのだから、あなたも自分の人生をやり遂げないと」と柔らかく微笑みながら言いました。
「俺の人生はあなたのものです」
「それじゃあ私が居なくなったらどうするの?私は前世の一言があなたを虜にしたことが信じられないけど、あなたが言うならそうなのでしょう。だけど、私が急に居なくなったらあなたはどうするの?」
「……俺も死にます」
ビルヘルムはラインハルトの膝に顔を埋めながら「行かないとは言ってくれないんですね」と残念そうに言い、ラインハルトはそこで自分から首から提げていた、ビルヘルムがかつてつけていた指輪を思い出し、ビルヘルムに渡しました。ラインハルトはそれがビルヘルムの母親のものだと思っていましたが、ビルヘルムはそれを親指につけながら「これはアマリリス・アラカンカスのものです」と言いました。
ビルヘルムは突然立ち上がってテラスの外を見ると、そのままラインハルトを抱き上げ、テラスから庭へ飛び降りました。庭に降り立ったビルヘルムはそのままラインハルトを抱えて初代皇帝の肖像画まで連れて行きました。
そこに描かれた指輪は確かにビルヘルムのものと一緒だった。唯一違うのは、元々金色だった指輪が今は銀色に色褪せていることだけ。しかし、リンケ侯爵の剣でさえ色が変わるのだから、金の指輪だって永遠では無いかもしれないとラインハルトは思いました。
ビルヘルムは指輪をそのまま床に落とし、「もう二度と輝かないもの」だと言いました。その意味が理解出来ずにいるラインハルトに、ビルヘルムは陰険な笑みを浮かべます。
「ラインハルト、実は俺はまだ言ってないことがあります。これを言ったらあなたは俺と結婚してくれるでしょうか」
ビルヘルムは笑っていたが、その目は全く笑っていませんでした。
「あなたが居なくなったら死ぬと言いましたが…それは俺の主人、あなたが俺のそばに居ないなら、それはあなたが死んでいるということです。それ以外にあなたが俺のそばを離れることはありません」
ラインハルトはその真っ黒な執着に鳥肌が立地ました。
「俺は自分で首輪を持ってあなたに向かいました。全部俺の欲に過ぎない。でもラインハルト、主人のいない奴隷を見た事ありますか?」
「あなたは私の奴隷じゃない…」
「俺は道化師にだってなるし、皇帝にもなる。でもラインハルト、それはあなたが望んだからです。でも、あなたが俺から離れるのは駄目です」
「あなたが何と言おうと、私はあなたと結婚はしない。そう決心したの。でも、あなたがそう言うと弱くなった私は結婚すると言い出してしまいそうになるから、もう言わないで」
「……言いたくなるんですけど」
「駄目。わかった?」
やっと二人は笑いながらイタズラをする恋人に戻りました。ラインハルトはビルヘルムが床に捨てた指輪を拾い、ビルヘルムの指にはめてやると「結婚指輪でもないのに、あなたが付けてくれるなんてわくわくします」と笑いました。
ミシェルの肖像画は既に別のところに移されていました。近々ここにはビルヘルムの肖像画が飾られる予定です。
前世の話が出て、ビルヘルムはヘルカに訪れた時、自分がどれほど震えながら食事をしたのかラインハルトに説明しました。それまで野蛮で汚いと言われていたビルヘルムは、ラインハルトにまで言われないか怯えてもいました。
ラインハルトは笑ってビルヘルムの頬に口付けを送りました。
「あなたが全部教えてくれました」
歯磨きも、自分を抱えて湯に入った事も、おとぎ話を夜に聞かせてくれた事も、全てビルヘルムは覚えていました。
ビルヘルムはラインハルトを抱きしめながら口付けをして、飾られた肖像画と彫刻が並ぶ中、二人は体を繋げました。その後皇太子宮に戻りましたが、二人の服装は乱れていました。そのまま皇太子の部屋に入ったラインハルトはベッドに引っ張られます。
「ねえ、私はあなたが時々ぞっとするくらい怖い」
「怖がらないでください。愛していますよ」
ラインハルトのシルクの靴下をビルヘルムが噛んで脱がせ、ドレスの飾り紐をたこのできた男の手で外されていると、ラインハルトは部屋の中に自分の少女時代の肖像画を見つけました。
「あれはちょっと恥ずかしいよ、ビルヘルム」
「恥ずかしがらないでください。俺の宝物です」
不穏だけど、この幸せイチャイチャ空間が永遠に続いてほしい…
ヘイツはルーデンの管理下になった小さな村を訪れていました。そこの村長に話を聞きながら村の人数を確認していると、遠くの家に狩人の娘が暮らしていて、その夫の話になりました。娘の夫は兵士で、野蛮族も撃退するという話を聞きながら、ヘイツは帳簿を書きました。
その三日後、ヘイツは実際にその兵士に会って、彼の身体の大きさに驚きました。フェリックスと名乗った男は、話を聞くとグレイシアと野蛮族の間で起こった三年戦争の終わりに負傷し、フェリックスは記憶を失ってしまいました。
リオニは負傷した男を助け、男の傷が癒えた後に素性を聞いたけど記憶を失っていて聞けず、そのかわり二人は恋に落ちました。
ヘイツは男と一緒に拾ったという銀のペンダントを観察しましたが、傷だらけで、それがどこの家門なのか分かりませんでした。
ヘイツはそのペンダントを持って村を離れ、オリエントに戻ってグレンシアで記録されたルーデンの出生名簿を見て、ようやく男が誰なのか知ることができました。それはラインハルトが最も大切にしていた騎士ディートリッヒでした。
ディートリッヒと同じ部隊だったマルクを連れて、二人はその夜にラフェルト村へ出立した。そしてマルクはフェリックスと名乗っていた男が間違いなくディートリッヒであることを目の当たりにして涙を流し、ヘイツはその様子を見てフェリックスにマルクを紹介し、彼の本来の名前がディートリッヒ・エルンストであることを伝えました。
すぐに領主に知らせたかったけど、そんなヘイツを止めてマルクは「引っかかることがある」と言いました。
マルクは当時のことを、振り返って話しました。
マルクはディートリッヒの部隊だったがビルヘルムを案内するために離れていたので、部隊では唯一の生き残りでした。
終戦後は遺族のために遺品を渡す回収班にまわり、そこでラインハルトの袖を見つけました。それはディートリッヒが支給品以外で唯一身につけていたのだったのでマルクはよく覚えていました。
マルクはそれをビルヘルムに届けました。それを受け取ったビルヘルムの顔は歪み、大笑いし、「こんなに呆気なく死ぬなんて」と言いました。マルクはそれを見て、父を失った子供の反応なのだと思っていました。
ビルヘルムが布を胸にしまうのを見て、マルクはその場を後にしました。そうして渡した遺品が、マルクはラインハルトの手に渡り、棺に納められているとばかり思っていたのです。
「……あなたは歪んだ独占欲のために遺品を渡さなかったと言っているわけですね」
「私の考えすぎと言うには……あの方は少し、人の範疇を外れることがあるので」
「確かに皇城で私が話している時も警戒していました」
「あの方は全ての男が嫌いなんです」
「その割には本人は乱れているのに」
夜の森に消えたビルヘルムとドルネシアを思い出してそう呟いたが、マルクに聞き返されてヘイツはすぐに「何でもありません」と返しました。
死亡した皇太子と、彼を殺した皇太子妃。マルクはビルヘルムが皇太子妃に指示したのではないかという疑問を持っていました。普通ならその場合、ドルネシアが欲しいからだが、ラインハルトのためにそうしたとしたら。
とにかく、ラインハルトにディートリッヒが生きていると報告したくても、ビルヘルムの反応が気になりました。
「例え独占欲があったとしても、既に亡くなった人の遺品を隠す理由はありますか?死者は戻ってこないのに」
「それでは他に理由があったということですか?」
「生きていることを知っていた。いや、それなら死んだという事実を確実にするはず。それなら他には……」
ヘイツは一旦言葉を切り、躊躇いながらも「本人が殺した?」と口にすると、すぐにマルクが「とんでもない!」と反応します。
「あの戦闘は仕方なかったんです!大族長が」と話し始めるマルクをヘイツは止めて、「ただの仮説でした。とにかくすっきりしないのは事実です」と話します。
ヘイツはすっきりしない事を放置しておくのも嫌だったのでこの件はもう少し調べることにして、その間ラインハルトには報告しないことになりました。
3巻前編を読んだ感想
可哀想なビルヘルムから始まり、不穏な空気とイチャイチャで感情が揺さぶられながら、ここにきてディートリッヒ生存!というジェットコースター回でした。
▼読んでいた時の私のリアルタイム感想です。
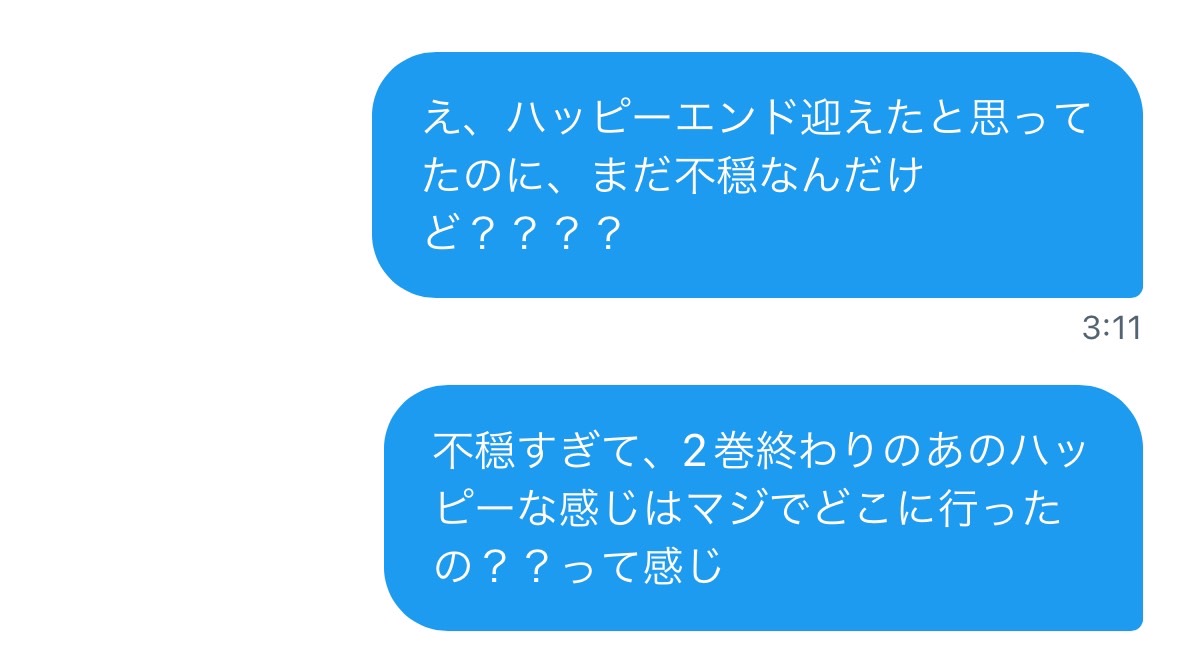
ここから怒涛の展開が始まっていきます…
次回の更新はtwitterにてお知らせします!